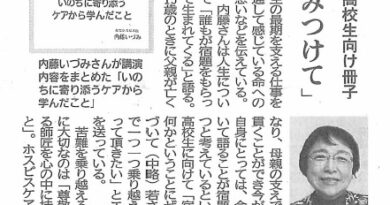永遠の別れから自分を取り戻す
 2012年4月28日中日新聞「あした野原に出てみよう(上)」より抜粋
2012年4月28日中日新聞「あした野原に出てみよう(上)」より抜粋
春になると山梨の盆地では梅、あんず、桜、すもも、桃と次々と芳しい花々が咲く。
冬の間にちぢこもった体のすみずみがその風景のなかで伸びてゆく。大切な人の存在を失った時、その美しい風景さえ心に届かない。
永遠の世界に旅立ってしまった大切な人とは二度とこの世では会うことはできない。
湧き上がる後悔と悲しみにどう向き合えばいいのか、医療者はどう援助すればいいのか。ホスピスケアの生まれた国ではグリーフケアという分野でこの苦しみについて長年研究がなされている。アルフォンスーデーケン神父は、別れを体験してショックを受けた自分から新しい自分になるまでの十二段階のプロセスを教えている。本当に新しい自分になれるのだろうか?
2011年3月11日の大震災以来、「絆」という言葉が多く使われてきた。山梨の田舎育ちの私にはこの「絆」には人と人が助け合う、結びつくという働きの裏に、軽くはない各々の果たすべき義務と責任が伴っていると知っている。この「絆」が各地にあった時代には、死を悼むということも孤立せずに、地域で緩やかに共有され支えられていたと思う。今は多くの地域で「絆」の重さから解きはなたれ自由になった分、悲しみや痛みを個人だけで抱えざるを得なくなってつらさが増している。
私が15歳の冬、52歳の父親が楽しい夕食の最中、突然脳卒中で倒れ、未明には帰らぬ人となった。その後の葬式や初7日の式も、まるで現実感のない夢のように過ぎていった。気づくと、私と母と弟が残されていて、大きな不安に包まれた。悲しみははっきりと自覚できなかった。
3ヶ月程して、ようやく父は2度と戻ってこないのだと思えるようになり、涙が溢れ、底なしの悲しみが襲ってきた。毎晩ふとんに入って母に聞こえないように声を押し殺して泣いた。それが何ヶ月も続いた。
幼い頃から文学が好きで、感受性の強い私が医者になり、しかも、必ず患者さんとの永遠の別れが待っているホスピスケアの分野を学んだことは、父との死別体験が深く影響している。私と父との別れはあまりに突然だった。しかし、がん患者さんの場合は違う。短いかもしれないが、残された時間がある一時も無駄にしてほしくない。病気が冶せなくても、最期の一息までその入らしく生き抜いてほしい。人生の残された課題(ライフレッスン)に気づいてほしい。和解したいことに直ちに着手してほしい。恥ずかしがり屋の人も、「あなたが好きだよ。大切だよ。ありがとう。そして、ごめんね。さよならだ」と、愛する人にはっきり伝えてほしい。言葉にしないと思いは伝わらない。
そのためには、がんによって起こる身体の痛みを緩和することが一番先に必要になる。がんの痛みは全てを押しつぶしてしまうから。だから、20年前から緩和ケアを必死で学んできた。がん患者が身体の痛みから解放され、自分を取り戻すために。
お子さんのいない仲良しのご夫婦に出会った。五十代のご主人は残していく奥さんのことをいつも心配していた。出会って一年後、その入らしく凛々しく立派な最期を迎えた。その後、奥さんはひとりで何とか暮らしていたが、私に聞いてきたことがある。
「先生、いつ泣かずに眠りにつくことができますか?」
「必ずその日がきます。そのためには今、思い切り涙が枯れるまで泣いてください。そしてあした、桃の花の咲きほこる近所の野原に出て深呼吸してみて。頬をなでる風にご主人の声が聞こえるかもしれない」と。
奥さんは半信半疑だった。
しかし、父を亡くして思い切り泣いた何ヶ月の後、野原に出た私には、父の静かな声が聞こえた気がした。心の目には白黒だった風景にその時豊かな色が戻ってきたのだ。その時が新しい私の始まりだったと思う。