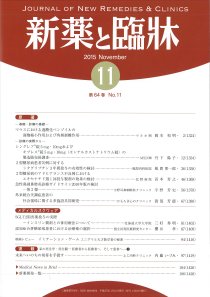「ありがとう、さようなら、そしてごめんなさい」と言えるために
 東京消防 平成23年1月号より抜粋
東京消防 平成23年1月号より抜粋
「在宅ケア」という言葉を最近よく耳にします。私かイギリスで学んだ「在宅ホスピスケア」という、いのちの最期の過ごし方を伝えはじめた一七年前、日本では「ホスピス」も「在宅ケア」も初耳の人が大半でした。「自分の家の畳の上で死にたい」という本音の気持ちはあっても、がんになれば病院で「治りたい」という希望のもとに最期まで入院しているという経過が当時はほとんどでした。
日本の八〇年代から九〇年代は、往診してくれる開業医は見当たらず、重症になった段階で退院し医療者から離れた家で安定して過ごせるということを皆さんは想像できないようでした。
「がんの痛みを緩和し、家で穏やかに過ごせる在宅ホスピスケアの方法をイギリスで学んできました」こういうことをいくら力説しても皆さんは否定的な反応でした。しかし、私は患者さんとの出会いに学びながら一歩ずつ進めてきました。現在では国の方針が後押しをして、課題は大きいですが、全国で少しずつ広がってきています。家に重病人がいることが増えていくと思います。
四五歳のFさんはその初めのころ知り合った、進行がん患者さんでした。初めての外来でこうおっしやいました。「二年前、直腸がんになり、その後転移して人退院を繰り返しました。僕は残された人生は一日も長く家族と一緒にいたい」
四五歳のFさんは、奥さんと中学生、高校生の娘二人との四人家族でした。やり残したことはたくさんあるはずで深刻な状況なのに、Fさんは私の前で穏やかに微笑みました。
「先生に会えて僕は安心しました。最期まで僕らしく生きられそうです。家族と一緒にずっといられるように助けてください」
その後、亡くなるまでのお付き合いは半年でしたが、平和に穏やかに過ごせるように私は最善を尽くし、何とか合格点はもらえたと思っています。
やがて病気が進行して、寝付くようになったFさんの周りを三人の家族が囲み、明るい笑い声や歌声が満ちました。Fさんの一家は音楽好きでした。
Fさんは「幸せだよ、ありがとう」と最期まで繰り返しました。その言葉は、Fさん亡き後もずっと奥さんや娘二人を支え続けていると私は思います。
ホスピスケアの第一人者である柏木哲夫先生は、こうおっしゃっています。
「起きるかどうかほとんどわからないのに消火訓練や避難訓練を毎年きちんとします。準備するわけです。しかし、私たち全員に必ず100%起きる、来たるべき『死』については、言い訳したり無視したりして準備しません」
日々、緊急事態に向かい合い、いのちをかけて働いてくださる隊員の皆様には既に必要ないことかもしれませんが、元気なときに(できれば元旦に?)自分の限りある生を自覚し、一日でいいからいのちと人生の貴さを噛みしめて準備する人が増えてほしいと思います。
そういう準備を重ね、別れの最期の日々に愛する人々に感謝とともに「幸せだよ、ありがとう。そして先に逝ってごめんね」と言えるような人間になりたいと私自身も願っています。