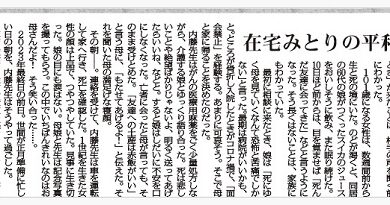温かい看取り議論活発に 日本経済新聞2010年1月17日より
 世界一の速さで高齢化が進む日本は、2038年には年間死亡者数が170万人に達する「多死社会」を迎える。終末期の医療、介護のあり方や看取りについて、国や専門家ばかりでなく、個人が十分な準備と覚悟を持たなければ、自分や身近な人の幸福な最期は望めない。
世界一の速さで高齢化が進む日本は、2038年には年間死亡者数が170万人に達する「多死社会」を迎える。終末期の医療、介護のあり方や看取りについて、国や専門家ばかりでなく、個人が十分な準備と覚悟を持たなければ、自分や身近な人の幸福な最期は望めない。
●欲求不満抱え苦悩
在宅ホスピス医として終末期医療に携わる内藤いづみと、少子高齢社会の家族ケアを模索する評論家の米沢慧の往復書簡『いのちのレッスン』 (雲母書房・ 2009年)は、生と死を自らの問題として考えるよき案内書といえる。
内藤は「医科学が発達し、いのちに対する多くの情報や回答を得たはずの現代に、多くの人は人との繋がりを失い、乾きにも似た際限のない欲求不満を抱えて苦悩しているように感じる。患者の権利は強まったけれど、幸せな患者は増えたのだろうか。何より、いのちの一部でもある〝死〟について、豊かに考える土壌はやせ細ってきていて心配だ」と問題提起する。
米沢は「死は敗北である」として延命・救命を主眼とする従来の医療を「往きの医療」と名付ける一方、自然死に向かって残された生を全うしようとする
患者に寄り添う「還りの医療」を提唱し、議論を深めていく。
また、診療所でホスピス医療を続ける徳永進と、詩人の谷川俊太郎との往復書簡『持と死をむすぷもの』(朝日新書・08年)は、徳永が臨床のエピソード、谷川は自らの詩萱父えながら、死にゆく人にとって和解の意味や死後の世界などについて縦横に論じ合う。
2つの往復書簡の底流に流れるのは、「終末期は人生を完成させるときで、医療者や介護者は専門的な技術と知識を駆使してそれを支える役割がある」と
いう思想だ。
多くの高齢者を看取ってきた茨城県つくば市の訪問診療専門クリニック院長、平野国実は『看取りの医者』 (09年・小学館)で、在宅医療の成否を決めるのは、訪問する医師や看護師、ヘルパーの連携と、家族による心身のケアーと指摘。核家族化でこうした機能が弱まっていることについて「かつて死を身近に経験し、死を具体的に感じることによって培われてきた〝人生の終焉に対する覚悟〟や〝潔さ″や〝諦観″といった価値観が、この数十年間で日本人から徐々に失われてきた」と指摘。その上で市内の高齢者アパート「ぽらりす」を「新しい家族システム」と紹介する。
「ぽらりす」はアパートの6室に認知症やがん患者を含む高齢者を受け入れ、6人のスタッフが24時間交代で常駐する家族的な雰囲気の中、日常の世話をし、最期も看取る。家庭の事情で終末期を自宅で過ごせない場合の「一つの選択肢となる」と平野はみる。フォトジャーナリストの國森康弘の『家族を看取る』(同・平凡社新書)は、行き場のない高齢者を手厚く介護する島根県知夫里島の「なごみの里」を密着取材。代表の柴田久美子さんの「死は怖れるものでなく、先に逝く人が蓄えてきた豊かな生命力を看取る者に渡す、幸福に満ちた瞬間」といった言葉や実践を通じて、温かい看取りをするための知恵や心構えを伝える。
●自宅で死亡は12%
終末期を自宅で過ごしたいと答える人の割合は各種の調査で60~80%に達する。しかし51年に82%だった自宅で死亡する人の割合は現在12%台。願いと実態との落差は大きい。
2000年代に入ると、国民医療費の増加抑制も狙い、厚生労働省が「施設から在宅へ」という方針を掲げ、入院が長引くほど病院の診療報酬が下がる仕組みを導入して退院を促したり、在宅医療の診療報酬を増やしたりした。
ただ、「これまでの医師養成は臓器別の専門医が中心で、幅広い症状に総合的に対応できる『家庭医』を育ててこなかった」(『家族を看取る』)ため、将来地域で高齢者を診療する医師が不足する恐れがある。質の高い「日本版家庭医」を増やしたり、介護サービスの質を向上させたりする検討が進んでいるが、「多死社会」に向けての課題はなお山積している。「ぽらりす」や「なごみの里」が放つ光にも目を向け、看取りの文化を耕す糧としたい。