患者、意志たちの「心の痛み」との闘い(アエラ2009年12月28日号より抜粋)
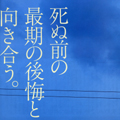 あの時、こうしていればよかった。一言、ありがとうと言えていたら-。終末期医療の現場に、薬では癒せない心の痛みと闘う人々がいた。人は、人生最後の後悔とどう向き合うのは。
あの時、こうしていればよかった。一言、ありがとうと言えていたら-。終末期医療の現場に、薬では癒せない心の痛みと闘う人々がいた。人は、人生最後の後悔とどう向き合うのは。
葬儀の後で、一葉の写真を差し出された。今年11月に撮られたスナップ写真だ。鼻に酸素チューブをつけた夫が、そばの捏ね鉢に向かっている。その姿を、妻が不安そうに見ている。妻は、こう話した。
「主人は、『これだけは、何としてもやり遂げる』という意志だけで立っていたんだと思います。すべて自分で決めないと気が済まない人でした」
山梨県甲府市の片桐伸介さんが、がんと聞い続けて4年日の秋だった。膀胱がんが腹に転移し、11月に入ると、立っているのもままならなくなった。
もう1度生き直す物語

英国で在宅ホスピスを学び、甲府市内で「ふじ内科クリニック」を開く内藤いづみさん(53)は撮影の4日前に片桐さんを往診している。彼は木曽漆器の捏ね鉢、特注の包丁などを譲る知り合いを、療養用のベッドがある自宅に呼びたいと訴えた。そば打ちの記録をまとめた分厚いファイルも見せられた。
「そば打ちの技術を、自分の手で伝えてからでないと死ねないんです」
電子部品メーカーの社長まで務めたが、58歳で早期退職するまで健康には恵まれなかった。
46歳の時、心筋梗塞で倒れた。
以後は、「おまけの人生だ」と話していた。リハビリを兼ね、そば打ちを始めた。休暇を利用して、全国1200軒のそば店をめぐり、その記録はファイル23冊になった。そば店を開いたのが2002年。歯ごたえがあって、のどごしがよいと評判になり、著名人も訪れる人気店になつた。膀胱がんが見つかったのは、その矢先だった。
その日、片桐さんは集まった知り合いの前でそばを捏ね、伸ばし、切った。発作を起こして倒れ込んだのは、そばを打ち終えた直後だった。
内藤さんが担当医になつた今年4月、片桐さんは悔いも漏らしていた。
「そば店の他にも、新しい事業のアイデアはいくらでもあるんです。環境ビジネスにも取り組みたい。あと3年ほしい……」
病状が進行するにつれて、無念を口に出すことはなくなつた。代わりに生きていた証として、そば打ちの儀式にこだわった。
そば打ちの数日後、内藤さんは片桐さんの病室を訪ねた。少年のような表情をしていた。「儀式はライフワークを締めくくるけじめだったのでしょう。ホスピスケアの現場には、人が人生を終えようとする時、もう一度生き直す『いのちの物語があります。私たちは、その物語に参加させていただいているのです』
そば打ちから18日後の12月7日、片桐さんは66歳で亡くなった。静かな最期だった。
「ま」の後に続く思い
死にゆく人の言葉は重い。おくった者の心に、いつまでも根雪のように残る。しかし、その胸底にある思いを、残された者がさらうことはできない。
作家で評論家の中島梓さんは、今年5月26日に56歳で亡くなった。11月に出版された闘病日記『転移』凄絶な最期が描かれている。
昨年、膵臓がんが肝臓に転移した。9月から日記を書いた。まあ、50こえるまで生きてたんだし、息子も25歳になったし、江戸時代なら平均寿命は50歳前後だったんだから
大好きな着物を着て出かけ、普段通りにライブも開いた。しかし、徐々に文章には、同じくがんの疑いで入院した夫、残されることになる息子への愛情がにじみ始める。亡くなる2カ月前には、こう記した。
それにしても目の前の空が青いというのはなんとも気持がいい。(略)やっぱり、生きているのはいい。生きていたいとあらためて思う。
5月15日に手書きになる。が昏睡状態になった17日の日付でパソコンに文字が残っていた。
-5月1
ま
そこで途切れていた。
闘病中も、栗本薫名で人気連作小説を書き続けていた。結局未完に終わった。最後の「ま」の後に続けたかった思いは、もう誰にも読みとれない。
5月に出た単行本『死ぬときに後悔すること25』が売れている。緩和医療医の大津秀一さん(33)が、これまで接してきた患者がふと口にした言葉から、人が死に際に後悔する25項目について、解説している。
後悔は大小、多岐にわたる。健康を大切にしなかったこと、会いたい人に会っておかなかったこと、愛する人に「ありがとう」と伝えなかったこと
大津さんは言う。
「患者さんの多くは突然死期が訪れ、きちんと家族や友人などに言うべきことを伝えられないまま、亡くなってしまう。残された家族も後悔するというパターンが少なくありません」
家族みんなで笑いたい
ずっと仕事ばかりしていた。家庭を顧みなかった。いつか家族とゆっくりと過ごしたい。笑って話したい。でも、遅かった。
そんな後悔を抱く男性患者は少なくない。
ベストセラー本『病院で死ぬということ』の著者で、東京都小平市のケアタウン小平クリニック院長の山崎章郎さん(62)は、20年前に担当した一人の男性が忘れられない。
40代前半のFさんは、胃がんにがんが転移していた。死の2週間前、入院先の病院から自宅に戻った。当時中学生だった子どもに「治らないかもしれない」と伝えた。
翌朝。朝食の席は気まずい雰囲気だった。と、息子がパンをのどに詰まらせた。その途端家族みんなが笑いだした。
営業マンとしてずっと、深夜に帰宅する日々だった。出張も多かった。家族と過ごす時間を持てなかった後悔が、胸を突いた。その日の日付で書かれた手紙は、こんな内容だった。
(これから先もずっといっしょにいられると思っていたからお前たちといっしょにいる時間のたいせつさに気づかなかったんだ。病気になって、しかもお前たちといっしょにいる時間がもうあまりないかもしれないときになって、お前たちといっしょに過ごすことのたいせつさや楽しさを知らなければならないとは、とても悔しい)
山崎さんは、Fさんと同年代だった。
(お父さんの闘いぶりはどうだったかな?なかなか捨てたものではなかっただろう)
という手紙の書き出しに、父親のプライドを感じたという。
「子どもの成長を見届けられない分、親父としては、せめて『生き様』を書き残しておこうと考えたのではないでしょうか」
人が最期に抱く後悔で重いのは、肉親との確執だろう。
前出の大津さんは、『死ぬときに~』を、死期が迫った70代の弟のもとに、秋田県から駆けつける80代の兄の話で締めくくっている。長年、疎遠だった。秀二さん(弟)の瞳から、一筋の涙がツーツと流れた。
「兄貴……」
「(略)兄ちゃんはな、秋田から飛んできたんだぞ!?わかるのか?」
声が震えている。お兄さんも涙をこらえているようだった。
父が残した生きる希望
鳥取県で「野の花診療所」を開く徳永進さん(61)は、詩人谷川俊太郎さん(78)との往復書簡『詩と死をむすぶもの』でこう書いている。
和解って、大切なことだけど難しい。ぼくら医療者は、死を前にしてるのだから、患者さんも家族も、お互いに心を大きくして、和解に辿り着こうよ、などと思いやすい。(略)ハッピーエンドを求めるくせがある。そして和解を目指してあの手この事と苦労し苦戦する。でも現実はそうならないことが多い。それでいい、と思う。
徳永さんは実際に、病床で父親が震える字で書いた謝罪のメモを、「今さら言われても」と突き返す息子を見た。
今年のベストセラー小説にも、疎遠のまま死を迎える親子が出てきた。村上春樹『1Q84』の主人公、天吾と父親だ。
きまじめで融通がきかない父と、天吾は幼いころから馴染めなかった。少年時代の記憶から、彼が本当の父親ではないのでは、と疑っている。30代になつた天吾のもとに、父親が入院している千葉県の療養所から、病状が悪化したという連絡がくる。見舞いに訪れた天吾は、固く口を結ぶ父に、静かに問う。
「たぶんあなたは僕にとって、血を分けた父親ではないのでしょう」「もしその推測が当たっているとしたら、僕は気が楽になる。(略)あなたを嫌いになる必要がなくなるからです」
父は、はっきりと答えない。が、天吾が療養所を去る時、父親の日から一筋の涙がこぼれるのを見た。翌月、天吾は昏睡状態になった父親を再訪する。
父親が寝ていたベッドの上には、白いまゆのような物体があった。その中に天吾は、小学校時代に強く惹かれ合いながらも別れざるを得なかった女性の姿を見る。天吾はその女性を実際に探す決意をする。父が残したのは、天吾にとっての生きる希望だった。死にゆく者が家族や周囲に託した希望が、人を動かすこともある。
「ママは死にたくない」
08年2月に36歳で亡くなったテレニン晃子さんは、娘と引き離される無念を、世の中の人々に託そうとした。自分の闘病と娘へのメッセージを綴った著書『ママからの伝言ゆりちかへ』の最後に、こう書いた。
この本をお読みになって、(略)ぜひ袖莉亜にお手紙を送っていただけるとうれしいです。
晃子さんは、福岡市内の会社に勤務していた02年、IT企業に勤務するロシア人のテレニン・レオニドさんと結婚した。妊娠した05年秋、悪性の脊髄腫瘍が見つかった。背中の痛みがあったが、病院では「妊娠しているとよくあること」と言われ、がんとわかった時は、悪性で手遅れになっていた。
06年に袖莉亜ちゃんを出産。晃子さんは、知人に「娘へのメッセージを本にしたい」と相談した。地元の出版社を紹介された。ノートやメモ帳、テープなどが07年10月にまとめられた。
本の中で、娘の将来を思って語りかけるメッセージは、優しくフランクだ。
(今日は先生が病気のことを話しました。ママの体はよくなりません。ゆりちかを産んで、かわいい赤ちゃんを産んで、お母さんが絶対必要なのですが、いっぱい話したいことあるんですけど、ママはあなたといっしょに生きることができないみたいです)
(女の子はかわいいほうが得だよ。お友達を作る秘訣は、オープンにすること。でも恋人には秘密を作って。ただし、一度セックスしたからって、彼女づらしないこと……(要約))
(子どもでいる時間は長くて、長くて、長いよ。ママは子どものころ、早く大人になりたいと思ってたかな。でも、本当に大人に近づいたら子どものままでいたいと思った。変だね)
詩のようでもある。が、最後は書けなくなり、テープに録音した。その声は涙声だ。(ママは死にたくないです。右足も左足も動かなくなっています。ゆりちかが抱っこできなくなるので、体が動かなくなるのは本当に怖いです。誰か助けて、私を助けてください。死にたくない、助けて)
読者からは袖莉亜さんに何通も手紙が来た。無念のバトンは、思わぬ方向にも届いていた。
今年、電通に勤めるコピーライターの梅田悟司さん(30)は、晃子さんの著書を原案にした絵本の仕事の依頼を受けた。
公私ともに世話になった50代の先輩社員が亡くなつたばかりだった。生前、彼から受け取った付箋を読み返した。
「結局、好きなことでしか成功できないから。楽しんでやりなさい」
独身で子どももいない。でも絵本『キミに残す手紙』 の文を書いた。
「生きる意味や後世に何かを残す大切さを考えるきっかけになれば、と思います」
夢の中での「授業」
アエラでは昨年、大分県の養護教師だった山田泉さんの活動を紹介した。ピンク色のスーツに身を包んで、自らの乳がんの体験をもとにした講演で全国を回っていた。記事掲載の直前、11月21日に49歳で亡くなった。
それから1年。大分県豊後高田市に住む山田さんの夫・真一さん(53)を訪ねた。
泉さんが亡くなった時に短大2年生だった長女は、福岡市内の大学に編入していた。将来は福祉や医療関係の仕事に就きたいと話しているという。
亡くなる数時間前、昏睡状態だった泉さんは、担当医だった大分市内のホスピス院長の山岡憲夫さん(57)や家族が見守る前で、突然、話し始めた。
「生きるということは、人のために生きること、以上」
50歳までは人のために講演を続けたい。その後は病気で悩む人たちの相談に乗る仕事をしたいと話していた。
山岡さんは言う。
「あの状態で声が出るということは、あり得ない。夢の中でも授業を続けていたのでしょう」
ただ、無念はやはり、家族に向けられていた。
「その時はさようなら」
長女は高校2年の時、不登校になつた。泉さんは乳がんの再発が発見される直前で、まだ教壇に立っていた。真一さんにいたたまれなさをもらした。
「学校の生徒には、いろいろな経験をさせているのに、自分の娘には何もしてあげられない」
真一さんへのメッセージがテープに吹き込まれたのは、余命を知った翌日だ。
私がいなくなったらどうします。いつものように市役所へ行って、いつものように市役所から帰ってきて。マミ(長女)やカズ(長男)はいい子に育ったと思いますけん。真ちゃん、カズ君やマミちゃんがこれから大変な日にあった時に、鳥が巣箱に帰るように安心して帰れる、そういう家の空問にしてください。
自分の命が終わるということで、どこかいつも意識し、わがままになつたり、投げ出してしまったり、真ちゃんにあたったり、真ちゃんにいやなことを言ってしまったりしたけれど、でも、そばにずっといて『僕が看取ってあげるからね』っていう気持ちで私を支えてくれたこと、本当にありがとう。3月の銀婚式まであと少しだけど、その日をめざしてもう少し気力を振り絞って生きていきたいと思います。でもどうしてもだめだったら……、その時は、その時はさようなら
講演では決して語られることのない、一人の妻として、母としての言葉だった。
最期を病院で迎えた泉さんの死は、医師を動かした。今年7月、山岡さんは在宅ホスピス専門の「やまおか在宅クリニック」を開いた。在宅にこだわったのは、患者が最期まで心から楽に過ごせるという理由からだ。
それでも、後悔の言葉を残して亡くなる人は少なくない。
「何でおれだけ早く死ななければならないのか。飲んだくれのあいつはまだ生きているではないか。」「あの人と結婚したのが悪かった。姑がいじめるからストレスがたまった」
山岡さんは、そうした患者と議論はしない。
「そうですね、辛かったんですね、と理解してあげることが、終末期医療では大事なのです」
患者の「支え」を強く
最期の日々に寄り添う緩和ケア医は、体だけではない、心の苦痛を和らげる「おくりびと」でもある。
横浜市の在宅療養支援診療所「めぐみ在宅クリニック」の小澤竹俊院長(47)は、この1年で149人を看取った。うち自宅で最期を迎えたのは105人だ。
緩和ケア医として、痛み止めを処方し、肉体的な苦痛を和らげる。一方で、患者が生きる「支え」を強くすることに心血を注ぐ。
「死に直面した方は、それまで当たり前だった食事や入浴、布団でゆっくり眠ることのありがたさを口にされます。後悔よりも、大切な何かに気づく。家族の存在、仕事への思い、趣味……いろいろ。それが、その人の『支え』になります」
がんを宣告された50代の銀行役員は、小澤さんに語った。
「息子には受験に勝てと厳しく接してきました。私は高卒で入行したので、大卒に負けたくない一心だった。リストラで人も切った。でも病気になって、競争で勝つより大事な、目に見えないものがあると知りました。
息子には、それを大切にできる大人になってほしい、とやっと言えるようになつたのです」 あるいはわが家が「支え」になるケースもある。
その小さな戸建て住宅は新幹線のトンネルの出口にあった。数分おきに轟音とともにサッシがビリビリと震える。それでも、余命を宣告されて退院してきた男性は妻と顔を見合わせて、「やっぱりわが家が一番だねえ」と
微笑んだ。長い歳月で育まれた愛着は、心の癒しになる。
小澤さんは「患者さんとの接触は最初の1回、2回が勝負」
と言う。早い段階で、人生の歩みを丹念に聞き取り、その人の支えを把握する。対話のポイントは「反復」にある。
ありがとうという希望
ある患者が「今日は、少し落ち着いています」と言う。「落ち着いて穏やかにお過ごしですね」と小澤さんは応える。
「はい」
「穏やかな理由は、何でしょう?」
「痛みがとれました。好きなビールも飲めた。庭の木に花が咲きました」
「そうですか。ビールが飲めたのですね……」
会話をくり返しながら、患者自身にも支えを再認識させ、落ち着きを保とうとする。
国立病院機構豊橋医療センターの佐藤健さん(52)が言う。
「できないこと、叶わないことが膨らんでいく死の過程にあっても、最後の希望は持ち続けられます。多くの人生の先輩を見送ることで確信しました」
同センターの媛和ケア病棟は全国でも有数規模で、年間約240人が最期の時を迎える。
こんな死があった。
50代の会社員のYさんは、他の病院から転院してきた時、生きる気力を失っていた。肺がんが骨に転移していた。モルヒネの量を増やし、ホルモン剤を補った。痛みが引き、食欲も回復した。
肺がんで呼吸は楽ではなかったが、自宅でくつろぎ、家族と温泉にも出かけた。そこで腰の骨を折り、再び入院した。
1カ月後、呼吸困難になったYさんは、佐藤さんに頼んだ。
「もう、死ぬまでずーつと眠った状態にできませんか」
「眠る薬はあります。でもだいぶ衰弱していて、眠ってしまったら、もう目覚めないかもしれない。それでも後悔しない?」
「もう十分、家族とは話しました。後悔はしません」
Yさんは、息も絶え絶えに答えた。妻も「そうしてあげてください」と同意した。Yさんはそばにあったメモ帳に、子どもたちへのメッセージを走り書きした。メモを妻に手渡すと、大声で妻に向かって叫んだ。
「おかあさん、ありがとう」
佐藤さんは、こう話す。
「死ぬ前の最後の希望とは、お別れに家族にありがとうと言えることではないでしょうか」
数時間後、Yさんは安らかな表情のまま、おくられた。


