宙を見ていのちを想う
(月刊MOKU 2016年9月号より)
夏の楽しみはたくさんあるけれど、私と夫が待ち焦がれているのは「真夏の夜の夢」。いや、甲府駅の広場で七月末に十日間開催される、「地ビールフェスト甲府」だ。
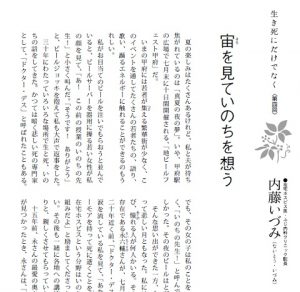
いまの甲府には若者が集える繁華街が少なく、このイベントを通してたくさんの若者たちの、語り、歌い、踊るエネルギーに触れることができるのもうれしい。
私がお目当てのビールを注いでもらおうと並んでいると、ビールサーバーを器用に操る若い女性が私の顔を見て、「あ! この前の授業のいのちの先生!」と小さく叫んだ。「そうです! ありがとう」と、ビールジョッキを抱えて私も大声で返事をした。
三十年にわたっていろいろな場所で生と死、いのちの話をしてきた。かつては暗く悲しい死の専門家として、「ドクター・デス」と呼ばれたこともある。
でも、その女の子は私のことを「死の先生」ではなく、「いのちの先生!」と呼んでくれたのだ。うれしかった。その夜のビールはとびきり美味いしかった。
そんな思い出ができた一方、今年の七月は私にとって悲しい月ともなった。私には、勝手に師匠と呼び、憧れる人が何人かいる。その中でも特に大きな存在である永六輔さんが、七月七日に亡くなった。
二十年近く前、「ドクター・デス」と呼ばれて悔し涙を流している私を見て、「あなたほど、明るくユーモアを持って死に逝くことを喋しやべれる人はいない。在宅ホスピスという分野はいのちを学ぶ重要な取り組みだよ」と励ましてくださったことは忘れられない。その後も一緒に各地への講演の旅へと出掛けたりと、親しくさせてもらっていた。
十五年前、永さんの最愛の奥さんに手遅れのがんが見つかったとき、永さんは、「家にずっと居たい」というご本人の希望を聞き遂げた。奥さんはいつも座っていた大好きなソファで娘さんに抱かれて息を引き取ったという。
最期をどうするか、という選択は、その状況になってから考えたのでは冷静に判断できないし、望んだ通りにできるとも限らない。元気なときからの勉強が必要だ。永さんは奥さんのがんが発覚するずっと前から在宅ホスピスの勉強をしていたから、「いのちは土に還る。だからなるべく土と暮らしに近い場所で最期を迎えたい」と決めていた。だからこそ奥さんの願いを聞き遂げ、自らも家で旅立つことができた。
永さんの晩年には、パーキンソン病、けが(骨折)、前立腺がんなど、病気との付き合いが重くのしかかってきたけれど、愚痴も漏らさず、自分のいのちに向かい合い、ぎりぎりまでラジオを通して各地の人々と繫がっていた。
骨折の手術から退院してすぐ、いささか強引ではあったが、車椅子で震災の後の福島市へお連れしたこともある。「なぜ自分だけが生き残った? なぜ故郷に住めない?」と涙する福島の人たちに、「はるかな星々のいのちにひと時思いをはせて、たまには思いきり笑おう」と語ってくださった。
永さんがお亡くなりになる二週間ほど前、ご自宅にお見舞いに伺った。永さんは深い眠りについていたが、付き添うご家族もご本人も、平和で穏やかな空気の中に居た。「家に居たい」という永さんの決心と、それを受け止めるご家族は見事だった。
声を掛けても、体を少しゆすっても永さんは起きてくださらなかったが、「永さん、ありがとうございました。今日はこれでお別れです」。そう耳元で声を掛けると、薄っすらと目を開けにっこりと笑った。
「たくさん旅に行き、たくさん見て、たくさんの人に会い、たくさん語り、たくさん愛し、たくさん学んだ。そしていまはとても幸せ」。そう私たちに語ってくださるかのような深い笑みだった。「ああ、永さんはもう何の心配もいらない境地にいらっしゃる。大丈夫だ」。私は安心していとまを告げた。
こうして七夕の日、永さんは鮮やかに天の川を越えて大きな星になったのだ。

