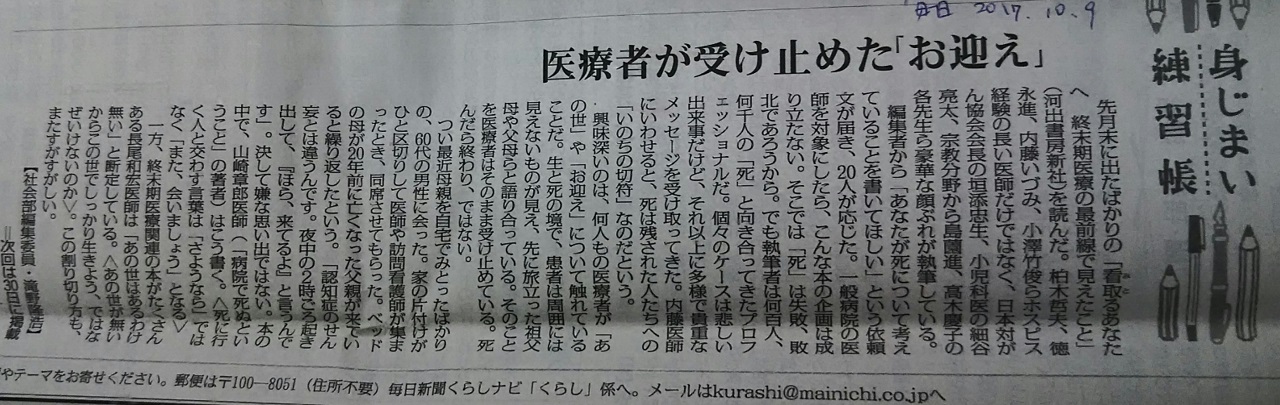対談 中村桂子・内藤いづみ「いのちを愛でる」
致知出版のサイトに中村桂子さんとの対談が掲載されました。
人間を学ぶ月刊誌「致知」2016年5月号特集「視座を高める」より
生き物たちが突然消えていく
中村 本当にお久しぶり。お忙しいのにわざわざ甲府から大阪まで来ていただいて、ありがとうございます。
内藤 先生はお変わりないというか、とてもお若いですよね。九年前にこのJT生命誌研究館で先生と対談をしたのがご縁の始まりでしたけど、その時は先生のお年のことは全然念頭になかったんです。ところが今回の対談に先立って先生か八十歳だと聞いてもうびっくりしました。でも先生、私も今年で還暦なんです。
中村 あら本当? 大きくなりましたね(笑)。それに大活躍。
内藤 いよいよ、これからだと思っています(笑)。ところで前にこちらに伺った時に、ビオトープ(小規模の生息空間)がすごく印象的で……。
中村 あれはビオトープというか、食草園といって、チョウのための庭なんですよ。
内藤 実はちょっと先生にお伺いしたいことがありましてね。食草園を見た後に、私も家の前にある二坪くらいの前庭に同じような空間をつくったんですよ。
そこには、例えば子供たちが蒔いたグレープフルーツの種が芽を出して、いまでは二メートルくらいの太い木に育っているんです。そうすると、その木の葉っぱにチョウチョが来るようになって。
中村 グレープフルーツはアゲハチョウね。
内藤 そうです。夥しいくらいの卵を葉っぱに産んでいくので、毎年木が丸裸になっていました。ところが、去年は何かおかしいなと思ったら、葉っぱが綺麗に残っていたんです。つまり1匹も来なかった。これって何だろうって。それから毎年十二月に咲いていたクリスマススカクタスが、去年は十月に咲いちゃったんですよ。
もしかしたら、いまの時代を百年後の世界から見ると、「あの時に変わったよね」ってことになるのではないかと感じているんですけど、先生いかがですか。
中村 二十一世紀に入ってから、気候と生き物の動きが変化してますね。うちでもカエルが突然来なくなりました。数年前は池が真っ黒になるくらいオタマジャクシがいたのに。それからハチもある日突然に消えて。
温暖化などいろいろ言われますけれど、本当の原因は簡単には分からない。人間の体のことも分からないことだらけでしょう。地球全体のことなんてもっと分かりませんでしょう。大きな流れとしては、地球は氷河期に向かっていますしね。
この前、地球という星の特徴を専門家にお聞きしたら、プレートでできていること、だからこの生態系もあると言われました。そのプレートが動いているから地震が起きたり、津波が起きたりするわけで、地球四十六億年の歴史は、そういうものであり、その中では、いまは優しい気候なんですね。
内藤 安定していますよね。
中村 もっとも地球の温度が上昇していることは確かで、変化は滑らかなものではなく大きな振れ幅がある。急に寒くなったり、暑くなったりしますね。そこではチョウやカエルは大変だと思いますよ。 ただ、大きな問題は、いまの地球環境の変化には人間が関わっていることですね。生命の誕生から三十八億年の間、常にいろいろなことがありましたけれど、それはすべて自然の動きでした。ところがいまの変化は人間が原因をつくっているところがあるのが間題ですね。
内藤 そうですね。
中村 人間も生き物なのだから、生き物の一つとして、どうすればよいかを仲間たちのことも思いながら考えなければと思うのです。
でも実際は内藤さんみたいに、チョウが来なくなったことにきちんと気づける人がどれだけいるか。
内藤 皆さんどこ吹く風という感じで(笑)。
中村 なーんにも感じていない人のほうがほとんどでしょうね。
毛虫の中に生命の本質がある
内藤 ところできょうは先生と久しぶりにお会いするので、その間に私ちゃんと成長したかどうかを先生に見てもらわなきゃと思っていて、ちょっとドキドキしながら来たんです(笑)。
中村 十分でしょう(笑)。私は内藤さんの在宅ホスピス医としての活動は本当に素晴らしいと思って、心から尊敬しているんです。
内藤 いえいえ、そんなこと。ただ、山や谷はありましたけど、前線から離れないで頑張れたのはよかったかなと思います。
中村 やはり現場で仕事をすることが大事ですよね。
内藤 そうですね。これは何も私だけじゃなくて、現場に踏みとどまって、いのちと向き合おうとする女性の看護師さんやケアマネジヤーさんたちが最近随分増えてきました。
中村 時代も少し変わってきましたね。皆さんの気持ちも。
内藤 ただ肝心の当事者がまだ弱い。皆さんの死生観がきちんと確立されていないものだから、医療の世界が総崩れになりそうなくらい、いま多くの現場で困っているんじゃないかと思います。
中村 死生観というのは、大人になって急に持ってくださいと言われても無理でしょう。生命誌の立場からは、小さい時から、どれだけ自然と向き合ってきたかどうかがと思うのです。
夏休みにサマースクールに行くとか、稲刈り体験に参加するとか、そういうことで子供たちに素晴らしい体験をさせていますと言うけれど、もっと日常を大切にしてほしいと思うの。この話をすると皆さんに笑われるのですが、孫が二歳くらいになった頃、一緒に外を歩いていると、道の端っこを指さして「あっ、ダンゴムシ」って言うの(笑)。時代が変わっても、やっぱり子供はダンゴムシなんだなと。
内藤 そうです。かわいいんですよ(笑)。アリもいますね。
中村 子供たちはそれを必ず見つけますからね。もちろん自然豊かな地方で育つのが一番よいけれど、そんなに大きな自然である必要はなくて、都会に住んでいても日常生活の中で接するような、ダンゴムシとか、小さなお花が咲いていますとかいうことはありますでしょう。
でもこの頃のお母様たちは、お稽古に子供を連れて行くにも、車に乗せてしまう。これだと子供と小さな自然との接点がなくなってしまいます。
内藤 本当はその時にしかない、子供の時間というのがあるじゃないですか。大事なことは、大人の時間に当てはめないことだと思います。
中村 そうね。おそらくそれだけでも、生きることと死ぬことを受け止められるような成長ができるようになっていくと思いますけどね。
研究館の開館十周年に「いのち愛づる姫」というミュージカルをつくって公演したんですけれど、そのもとになったのが平安時代に書かれた『堤中納言物語』にある「蟲愛づる姫君」です。そこでは毛虫が好きで飼っていて、皆に気味悪がられている十三歳のお姫様がこう言うんです。
「汚い毛虫が成長して綺麗な蝶になる。よく見ているとこの毛虫の中に生命の本質があることが分かり、毛虫を愛づる気持ちが生まれるのよ」
子供の視点は、物事の本質を見抜く力を持っているんですよ。それを大事に育ててあげたいですね。
主流と本流 そのどちらを選ぶか
中村 うちは今年で開館から二十三年経ちますけど、内藤さんもクリニックをつくられてからそのくらい経ちますよね。
内藤 平成七年にっくっているので二十一年になります。
中村 お互い二十年以上やってきたわけだけれど、最近現場でどんなことを感じておられますか。
内藤 末期の患者さんが在宅で最期の時間を過ごす応援をしようという志を立てたのは、医者になってすぐのことなので三十年以上前になりますけど、とにかく最初の頃は何の制度もなかったんです。
当時は病院で亡くなる方が大半でしたけど、病院ってやっぱり最期を過ごす場所としては適していないんですね。だから患者さんは帰りたいと思うけど、誰もしていないことだから勇気がいる。
それでも帰りたいという人との縁があった時に、いろいろと障害はあってもそれを一つひとつ乗り越えてきました。ところが最近になって国が方針を変えたんです。
中村 急に在宅へと変わりましたね。
内藤 もう瞬く間に。でもそれって、本人たちの気持ちを汲んで家で過ごすのを応援しましょうというのではなく、病院や施設ではお金がかかるから家に戻ってくださいということなんです。
中村 すべて経済で動くのね。
内藤 だからいま、当事者はもちろん、家族も自治体の行政も皆さん困っているんです。でも先生、国がやると速いですね。私か三十年以上かけてやろうとしてできなかったことが、大河の流れのように、形の上ではありますけどアッという間にできてしまった。
これまで私はずっと支流のほうで、出会った方とじっくり向き合ってきました。やっぱり大量生産はできないんですよ、一つのいのちに向かい合うというのは。
ゆっくりゆっくりいのちの声を聞いていくのは、子育てに似ているかもしれません。その聞こえるか聞こえないかの微かな声を聞くことをしてきましたから、夫には「いづみの趣味のクリニック」つて言われてきました(笑)。
中村 それが大事。だからこそ続けてこられたのでしょう。
内藤 いまは医療保険などのバックアップを受けられるので、昔よりやりやすくはなりました。ところがその一方であまりに手厚すぎるようになったせいか、地域がすっかり変わりましたね。
中村 具体的にはどんな変化ですか。
内藤 お年寄りの姿が見えなくなったんです。なんせ少しでもその方に老化現象が出てきたら、デイケアといった介護保険のシステムに乗せられてしまうんですよ。
最近、一つ悲しい出来事があって、その方はちっちゃな手芸店を営む百歳のおじいちゃんでした。
「本流を貫くには細々とやっていくしかなくて、苦しいこともたくさんあるけど、主流に流されないようにしないといけないですね」
医者に言われたからと、四十五年前から毎朝四時に起きて、二時間散歩を続けていたんですね。家には家族と住んでいて、四坪くらいのお店が生き甲斐で、一年に一回インフルエンザの注射を打ちにくるだけで介護保険にもかかっていない。そうやって自立していて、しかもおしゃれだから私のクリニックではヒーローでした。
ところがある日、ケアマネジャーに声を掛けられたんです。
中村 そんなに元気なのに?
内藤 ご高齢なので歩く速度はほとんど芋虫くらいでしたからね。
あちらもビジネスとしてやっておられるので当然と言えば当然なんですけど、おじいちゃんに「何て言われたの」と聞いてみたら、「温泉があるしカラオケができる」と言われたって。
いまはそのお店のシャッターは下りていて、一日も開かないんです。きっとすぐに車椅子に乗せてもらうことになるから、身体能力もどんどん落ちていくので、もう二度とあのお店のシャッターは開かないだろうなって。
中村 それはとても残念な例ね。
内藤 こういったことは他にもたくさんありました。ですから、お年寄りの方は、頑固老人になってくれればと思うんですよ(笑)。ここでいいから、行かないよって。
中村 でも、そこが難しいのよね。大きな流れができると、それに流されてしまうでしょう。内藤さんのお仕事で言えば、医療の世界が経済的な理由とはいえ、上手に動かせばいのちを基本的に考えましょうという気持ちを、生かすことができる流れになってきたわけですね。
ところが大きな流れになると、先ほどのおじいちゃんの例が示すように、本質が見失われてしまうわけでしょう。よさそうに見えても、実は違うというのが辛い。
内藤 主流派と本流派という見方があって、先生や私は本流を常に目指しているわけですけど、そこに主流というのが出てくると。
中村 なるほど、本流と主流。いいこと言うわね、あなた。
内藤 これは淀川キリスト教病院理事長の柏木哲夫先生に教えていただいたんですよ。とにかく本流を貫くには細々とやっていくしかなくて、苦しいこともたくさんあるけど、主流に流されないようにしないといけないですね。
本当に大事なことは二十年かかる
内藤 先生は最近どんなことを感じておられますか。
中村 私は直接人間に関わり合うようなことはしていなくて、毎日付き合っているのはチョウやクモ、カエル、イモリと…(笑)。
内藤 でも先生のすごいところは、生き物が発するメッセージを皆さんに分かりやすい形で伝えられていることですよ。
中村 私は科学からスタートしていますから、科学的に物事を考えたり、生き物を科学的に理解することはとても大切なことだと思っています。でも、科学だけですべてが分かるわけでもないし、逆に抜けているものもたくさんある。
その一つが時間です。
生き物って何ですかと聞かれたら、私は時間を紡いでいるものと答えます。それなのにその基本である時間を抜きにして切り刻んで考えても、それは生き物ではありません。
生命誌は簡単に言うと、三十八億年もの長い間連綿と続く生命の歴史を紐解こうというものです。
生き物の歴史には時間と、驚くほど様々な生き物の関係が存在します。ところが科学はこの時間と関係を切ってしまうので、生命誌でそれを取り戻したいと思って始めました。
最初の頃は、何をやるの? みたいな感じで、理解してもらえませんでしたけれど。
内藤 ああ同じですね。そこから苦難の道を歩まれたと。
中村 苦難とは言えない。少数派を楽しむ気持ちです。二十周年の時に、これまでやってきたことや自分の思いをまとめたんです。皆さんにお知らせしようと。でも、それを見て一番納得したのは自分でした。私はこういうことをやりたかったんだって、明確に見えてきた。
二十年って生まれた赤ちゃんが大人になる時間でしょう。そこで、本質的なことをきちんとやりたかったら、二十年要るんだなと思いました。
ところがいまは大学などでも、与えられる研究期間は三年、長くて五年。三年で成果が出なければ、それで終わり。十年とか二十年かけて見てくれるところがなくなっています。でも私のいまの実感としては、何か本当に大事なことをやりたかったら、それくらいの時間が必要なのではないかということです。
内藤 私も二十年経ってようやく地元の方々に認知されるようになりました(笑)。
それと先ほど先生がおっしゃった時間と関係のお話は、まさに終末期にも通ずることなんです。人生の最期を迎える人たちの時間の意味と、それまでに過ごしてきた人たちとの関係。この二つを見直すことが、私たちの仕事の柱でもあるんですよ。
中村 時間と関係は、生きることの基本ですものね。
時間の場合、技術開発をしてある製品の製造時間を短縮することはできても、子供が生まれるまでの十月十日を長いから二か月にしようというのは無理でしょう。やはり生き物には時間が大事なわけで、無駄に見えるかもしれない時間を過ごしていくことが生きていくことなんですよね。
内藤 そうやって生きる意味を見つけていくと。
中村 そう。そのことを皆さんにぜひ分かってほしい。
内藤 同じですね。私もずっとそう思っていました。
人のいのちの責任を持つ仕事
内藤 私かこの二十年間を振り返って一番大きい変化は、患者さんにモルヒネなど痛みを和らげる薬をたくさん使わないようになったことです。昔はもう力ずくで痛みをゼロにしてあげようと躍起になっていたものだから、山梨県内で一番モルヒネを使う医者でした。
いまはそういった薬をあまり使わないでも患者さんの痛みをうまく緩和して見送れるようになりました。
中村 それは素晴らしい。
内藤 その見立ては、やはり二十年の蓄積かなと。人にはそのコツをなかなか教えられないのは、二十年苦労しないとダメなんでしょうね。看護師さんたちにぱ「内藤マジック」だって言われるんですよ(笑)。何であの先生の患者さんは苦しむのに、内藤先生の患者さん
はモルヒネをたくさん使わなくても最期までその人らしく幸せなのか不思議だって。
中村 それこそ時間の積み重ねでしかできないことでしょう。
内藤 最近の患者さんのお話をすると、その方は山梨県内の山奥に住まわれていました。最初は家族と八十五歳のご本人がクリニックに来られて、ぜひ私に診てもらいたいと。胃カメラのデータを見せていただいたら、胃の入り囗に大きながんがあって、医者には余命が厳しいと宣告されました。
でもご本人は、病院は嫌だと。自分が暮らしてきたところで最期の日を迎えたいと言い張るので、では一緒に頑張りましょうと。それから定期的にお伺いしましたけど、何も大変なことが起こらずに、結局モルヒネも一回も使わないままに八か月で安らかに逝かれました。
中村 苦しむことなく。
内藤 ええ。それであと一週間くらいかなという時に往診に行きましてね。その日は親族の方がいっぱい集まっていてとても賑やかで、ご本人もニコニコされていたんです。ところが私たちが着いた途端、奥さんに「俺のことはいいから先生たちにご馳走を出すように」と
言い出しましてね。でもずっと看病しているわけだから、そんな暇はないわけですよ。
そのうち本人が怒り出すものだから準備が始まって、山菜料理やらいっぱいご馳走が出てきて、皆さんと一緒になって飲み食いしたんです。それがすごく楽しくて私たちは幸せで、その様子を見ているご本人もとても楽しそうでした。
中村 眼に見えるようだわ。
内藤 その時、私ふと思ったんですよ、これって体験したことがあるなって。何だろうかと考えたら、田舎の葬式の後によくやっていた宴会だったんです。だからある意味、本人が参加しているお通夜みたいな感じで。それが亡くなる五日前のことでした。この時改めて患者さんを看取ることも祝祭になるんだなと思いました。
中村 いいドラマの完結ですね。
内藤 でもこればかりは毎回最後の最後まで分からないんです。途中で本人がギブアップして人院しちゃう人もいるし、家族がダメという場合もある。だから一つのドラマを「ご臨終です」というところに持っていくまでは、ずっと緊張感が続くんです。
中村 私たちのように、自分の都合でスケジュールを組むわけにはいかないのだから、本当に大変なお仕事ですよね。
内藤 人のいのちに責任を持つ仕事ですからね。でもその覚悟を決めさせてくれたのは、私が二十七歳の時に病院で出会ったユキさんというがん患者さんでした。彼女は当時二十三歳で、いずれは無数の管が繋げられて身動きできないままベッドで最期を迎えることが予想されました。
私、彼女に聞いてみたんです、「どうしたいか」って。そうしたら「家族と過ごしたい」と。それで私か往診することを約束して、彼女の望みを叶えてあげたんです。でもそれからは病状の急変が心配で一日に何度も電話を入れて確認したり、夜間の急変に備えてポケットペルをすぐ近くに置く生活が続きました。もう二十四時間、自分の自由になる時間は全くなかったんですけど、ある時ユキさんがこう言ってくれたんです。
「先生、私ね、大学病院の先生が百人いなくてもいいの。私には内藤先生がいるからいいの」
その四か月後に彼女は母親の腕の中で逝きました。いま振り返ると、私は彼女に出会ったからこの道を歩んでいこうとしたのではなく、自分の道に彼女がいてくれたんだと思うんですよ。
中村 まさに出会い。仕事の中で大事なのはそういう出会いね。
内藤 ええ。いのちに向き合う医療をやりたいという気持ちはそれ以前からずっとありましたから。
ただ彼女は私か最初に看取った患者さんでしたので、いろんなことを教えてくれた先生でした。
決して人間だけが特別ではない
内藤 きょうはせっかくですから、先生がこの道に入られた経緯もお聞かせいただけますか。
中村 私かDNAのことを知ったのは、大学三年の一九五七年でした。その数年前にDNAの構造が発見されたわけで、日本ではそれを知っている先生は数えるほどしかいらっしゃらない時。そういう時代に、たまたまDNAのことを教えてくださる先生と出会って、これは面白そうだとこの分野に入りました。
卒業後には三菱化成生命科学研究所で生命科学という新しい分野に入り、これも楽しかった。ただ当時は先生から吸収して、面白い面白いとやり続けていただけなので、自分でこれをどうしてもやりたいと考えることはなかったんです。
それが四十代の終わりくらいに、生まれて初めて、自分はどうしてもこれをやりたいと思うことができてきたの。
内藤 それが生命誌ですか。
中村 そう。きっとそれまで一所懸命学んできたことが少しずつ自分の中にたまってきていたんでしょうね。そこから、このままでは何かおかしいぞという気持ちが湧いてきたんだと思います。
内藤 何かが見えてきたと。
中村 その間に結婚をして、子供が生まれたこともありますけれど、当時日本は経済成長の真っただ中だったでしょう。その一方で様々な環境問題が出てきているのに、それを科学者が考えないのはおかしいと思ったんです。運動家になって反対を唱えても仕方がない。
でもその負の部分を無視したくないと七、八年は悩みました。
内藤 そんなに。
「生き物には時間が大事なわけで、無駄に見えるかもしれない時間を過ごしていくことが生きていくことなんですよね」
中村 そうしたらある日、生命誌研究館をやればいいと、突然頭に浮かんできた。その頃はよくお友達に電話で相談していたんですけれど、その時は確か夜中でした(笑)。
でも最初の頃は私か何をやりたいのか分かってくれる人は少なかったですね。いくら説明しても、それをやったからってどうなるの?みたいな(笑)。
地球上にいる何千万種もの生き物たちがDNAの入った細胞でできているのは偶然ではなく、三十八億年前にいた一つの先祖から生まれてきたからです。生き物すべてが繋がっているというのは、当たり前のこと。もちろん人間もその繋がりの中にいるわけです。
ところが環境問題を起こしたりしている時の人間は、自分たちだけがその繋がりとは別のところにいると勘違いしていると思うのです。そうではなく、自分たちも生き物なんだということを意識しながら研究をしましょうというのが生命誌で、これが生命科学と一番大きく違うところです。自分たち人間だけが特別で、生き物たちを支配してやろうというのではなくて、自分も生き物だという感覚を共有したいというのが、生命誌を研究する一番の目的です。
そうすれば、随分と人間も優しくなるんじゃないかと思いますね。
内藤 科学技術が発達すると、どうして人間も進化したと思ってしまうのでしょうね。
中村 確かにそうね。むしろ退化していて、縄文人のほうがよほどしっかりしていたかも。それだけにそういった勘違いを正すことができれば、人間はもっと謙虚になりますよ。
肉贓 私ね、『万葉集』が大好きなんです。その中に山上憶良のこんな歌があるんです。
若ければ道行き知らじ賄はせむしたへの使ひ負ひて通らせ
憶良は幼い子を何人も亡くしているんですよ。だからあの世から来る使いに賄賂を渡す代わりに、まだ幼くて歩けない我が子を負ぶっていってくれよと歌っている。
憶良は千三百年前の人ですけど、子を思う親の気持ちはいまと少しも変わってないんですよ。
中村 変わってない、大事な気持ちですね。
内藤 だから皆何となく偉くなった気でいるかもしれないけど、そんなこと全然なくて、どこかで立ち戻らないといけないですね。
患者さんとともに死の淵を歩く
内藤 ちょっと話は変わりますげど、実は二年前に体調を崩した時期があったんですよ。
中村 どうされたのですか。
内藤 かれこれ五十年くらい付き合っていた幼なじみががんになって、もう手遅れだってことが分かったんです。
それで緩和ケア病棟に入るまでも含めていろいろお世話をしたんですけど、その時にプロとしてではなく友人として彼女の最期に肉薄しちゃったんですよ。それがものすごく辛くて、相当まいっていたら、今度は四歳下の弟が脳卒中で倒れちゃって。
中村 それは大変。
内藤 そうしたら、それがショックで九十三歳の母まで具合が悪くなって、調べてみたら胆嚢がんが見つかったんです。母は以前乳がんの手術をしていたので、もう死ぬまで手術は嫌だと。私かホスピス医だから痛みがないように看てくれれば、それでいいと言うんですよ。
そんなこんなでいっぺんにいろんなことが起きたので、心身ともに消耗して患者さんもあまり診られなくて、経営のほうも危なくなってきたものだから、もう閉めようかというところまで行ったんですよ。でもそこから少しずつ好転して、母のがんも落ち着いて、弟も杖はつきますけど仕事ができるまで回復したんです。私も回復しました。
中村 それはよかった。内藤さんのためにも、患者さんたちのためにも。
内藤 一体これは何だったのだろうかと考えた時、私は幼なじみの死を通じて一人称の死を体験したのだと思ったんです。患者さんと一緒に死の淵を歩くには、相当頑張らないと一緒に落ちてしまうんです。私はずっとプロとして燃え尽きないように鍛えてきたつもりでしたけど、どうやら友人と死の淵を一緒に歩いている時に、部分的に落ちてしまっていたみたいなんですよ。
中村 でもそれを乗り越えたことで、一つの脱皮があったわけね。
内藤 そうですね、まさに脱皮だったと思います。
いのちは繋がっている
内藤 でも、そうやって苦しい思いも随分してきましたけど、私はいのちについて学びたいとずっと思っていたので、一人ひとりの患者さんと最期に至るまでのプロセスを一緒に体験させてもらって、本当に多くの学びを得てきました。
例えば人間というものには、生まれてくる時に頑張れる力があるように、死ぬ時にも逝く力が実はちゃんとあるんです。でもそれが最先端医療の中で多くの人たちが見失ってしまっているので、そういう力があることを伝えていきたいですね。だっていまのお年寄りたちの大半が、どうやって死ぬのか分からないという不安を抱えているのが実情ですから。
ただし、生きていくことを積み重ねていった先に死があるということも学ばなければいけません。
それには人との関係が大事で、例えば自分は一人ぼっちだという人には、あなたがここまで生きてきた中でずっと一人ぼっちだったはずがないのだから、振り返ってもらう。そしてこれから一人ぼっちで死にたくないなら、努力しなければいけないことを学んでほしいですね。
私ってものすごく好奇心が旺盛なんですよ。だからこういったことは、いまある学問の枠に入りきらないんです。哲学でもないし、福祉でもない。
中村 人間そのものを診るということね。
内藤 そう、全部ですね。そしてそこで学んだことを自分だけの納得で終わらせることなく、周囲に伝えていくと。それがいのちを繋ぐことに結びつくと思うんですよ。
中村 以前、お子さんのいない方が、「自分の遺伝子を残さずに死ぬのが辛い」とおっしゃったので、「実はあなたと同じDNAは、大勢の人々はもちろん、庭に来る鳥にも木にも花にもあり、ずっと繋がっているのです」とお伝えしたら、安心しましたと言われたことがあ
りました。「生きる」とは本来、哲学や文学などで問われるものですけど、科学でも人の役に立てると思うんですよ。
内藤 いのちを繋いでいくっていうのはいろいろな形がありますけど、それを当事者が認識することが死の恐怖を乗り越えていく一つの勇気になるのだと思います。
中村 そうですね。
内藤 今回の対談では「視座を高める」というテーマをいただきましたけど、生命誌というのは三十八億年の歴史からいのちを見ようとするもので、それ自体とても視座が高いですよね。
中村 物を見る時には二つの視点があって、一つは鳥のように全体を見渡すことです。そしてもう一つはアリのように、地面を這うようにして目の前のものを見ると。
私、最初に現場が大事だって言いましたよね。それってアリの目でしょう。どんなに立派なことを囗で言っても、現場のことを知らなかったら、話が具体になりません。だからこの二つの目を持つことを心掛けてきました。
内藤 能の大成者世阿弥が『花伝書』の中で役者について「我見」「離見」「離見の見」の三つの視点を説いているように、自分を見ること、相手の立場から自分を見ること、そして人間関係全体を俯瞰して見ることを私は大事にしてきました。そうすれば自分を笑える余裕であったり、ユーモアを言えるようになると思うんですよ。いのちに向かい合う仕事にはそれがないと潰されてしまいますからね。
だから、私は往診に行ってもいつも皆さんとゲラゲラ笑ってます。
二割泣いて八割笑っている感じ。生きるってことはシリアスじゃなくて楽しいことなんですよ。
それと先生がおっしゃったように、細々とでも現場を持っていないと、皆さんに伝えられる話が生まれないので、患者さんとの出会いって大事ですね。
中村 きちっと現場を見る目は本当に大事。そこにあるものはすべて宝物ですから。
内藤 本当にそうです。宝物との出会いですよね。