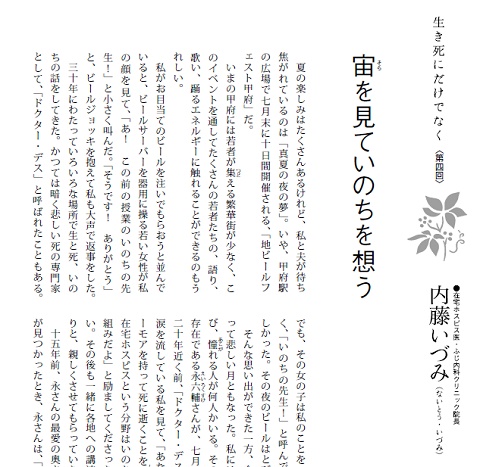命の文化を耕す在宅ホスピス医
遺族のボランティアとともに命の文化を耕す在宅ホスピス医
1995年に故郷の山梨県でふじ内科クリニックを開業した内藤いづみ院長。在宅ホスピス医としてがん末期患者の外来診療や訪問診療の傍ら、英国で学んだホスピスの理念を伝えようと全国で講演、著書や新聞連載でも積極的に情報発信を続けてきた。
「在宅ホスピスを通して、命の文化を耕したい」と言う。医療の枠を超えた文化運動は、患者の遺族約50人がボランティアで支える。
バンブー2009年2月号より抜粋
英国のホスピスの理念を講演で全国に広める
「主人のお見舞いに大勢の友人が自宅にやって来てね、足の踏み場もないはど。最期の1カ月はまるでお祭りみたいで楽しかった」。6年前に当時75歳の夫を在宅で看取った女性が振り返る。「内藤先生が診てくれるのなら、病院より家で死ぬほうがいいって、私の経験をみんなに伝えたい」
内藤いづみ院長は、夫の勤務の都合で1986年に渡英。丹精に育てた庭の花を眺めながら満足そうに亡くなる高齢者ら、ホスピス発祥の地で見た光景が今でも忘れられない。「日本でもホスピスの理念を広めたい」と、95年にふじ内科クリニックを開業した。
医師は内藤院長1人、職員5人の小さな診療所で、一般内科とともに取り組んできたのが在宅ホスピス。がん末期の患者を中心に、外来と訪問診療で常時20人ほどを受け持つ。「在宅ホスピスの主役は患者さんとご家族。限られた時間を幸福に過ごしてもらうためにお手伝いをするのが私の立場です」
幸せな時間を過ごした記憶は家族の救いになる。患者が亡くなった後、遺族が今度はボランティアで内藤院長の講演会を運営したり、別の患者と家族を支える側に回る。「ご家族は患者さんからもらった命のメッセージを活かし、伝え続けてくれる人になる。私も知らないところで命が回っている。それがうれしい」と言う。
診療の傍ら続けた講演会は700回を超えた。対象は医療者が半数、残り半数は市民と小・中・高校生。学級崩壊寸前の小学校で命の授業を受けもったこともあり、4年前には山梨県教育委員会委員長も務めた。

講演を聴いても「ホスピスは福祉」「死は医療の敗北」と捉える医師は多く、ホスピスの重要性を理解してくれる人は3%ほどだという。
「でもね、その3%に訴えていくことが大切だと思います」
帰国して18年。日本に緩和ケア病棟は増えたものの、英国で経験したホスピスとはまだまだかけ離れている。「日本の緩和ケア病棟はあくまで病院機能の一部。死は怖いもの、との認識が患者さんにもご家族にも、医療者にもあり、病棟に寒々としたものを感じる時もある」と指摘する。
病院とは違い、家には命のエネルギーの循環がある。患者が旅立つ時の辛さをなでたり、さすったりして癒すことで、患者から家族に命の受け渡しがある。生と死が病院に管理された現代にあって、「生まれた時に助産師がいるように、荏宅ホスピス医として人生の最期に寄り添いたい」と言う。
仕事の半分以上はボランティア。熱心に取り組んでも、高い収益が望めるわけではない。「在宅医療の医療費は病院医療に比べれば安いが、その分、たくさんの献身と愛情と信頼が必要になります」
最近は国の医療費削減政策で、病院から半ば強制的に退院させられる患者も増えている。山梨県でも都会と同じように独居だったり、家族関係が壊れていて、在宅医療の基盤ができていない例も多い。
だからこそ、地域に医療だけでなく看取りの文化が必要になる。
「荏宅ホスピスは患者さんとご家族が命に向き合う場。そこには『ありがとう』と『さようなら』が一つになる瞬間がある」と内藤院長。これからも地元で、全国で命の輝きを伝え続けていく。