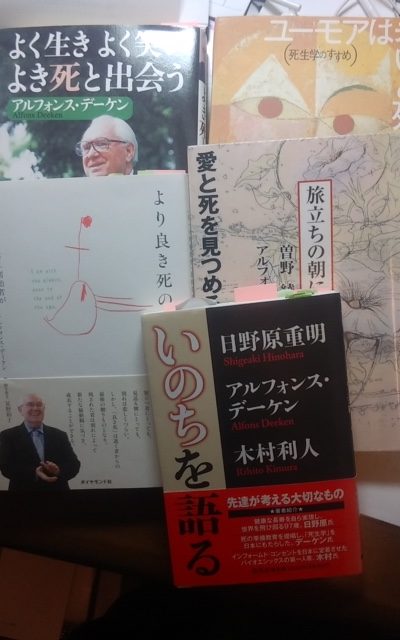往復書簡(米沢慧様)Vol.6 復
立春をすぎて梅の便りがとどき始めると、何となく落ち着きません。
蜜柑で冬をこして、いま伊予柑。そして八朔、甘夏とつづく柑橘類を賞味し終えるころに桜満開。これがわたしの例年の早春符なんですが。
さて、今月は「最近の緩和ケアのあり方に疑問がある」という在宅ホスピス医内藤いづみさんからの問題提起です。襟を正してお応えしなければなりませんね。
わたしはがん対策基本法が施行された時点で「緩和ケアはあらたな段階に入った」「緩和医療は転位した」というように書きました(『選択』2008年3月号)。その根拠になったのは前年にがん体験者の自助グループ主催の講演会で聴いた伊藤真美さん(花の谷クリニック院長・千葉県南房総市千倉)の講演でした。伊藤さんは地域に根ざした有床診療所(緩和ケア病棟10室14床)をたちあげて10年、勤勉なお医者さんとして知られています。緩和ケアを求めて入院された患者であっても延命をのぞんでいること、それに応える緩和医療をめざすという話でした。具体例を示しながら化学療法、放射線療法、胃瘻、腸瘻を作る外科的処置をはじめ、根治ではなくても必要に応じた手術や代替医療まで可能だとして“がんとの共生を支える緩和医療選択の時代”に入ったと明言されたのです。
「緩和医療医としてその終末期医療を支えながら、一方、高度な先進医療に患者さんを繋いでいくという最大限の努力をしていかなければいけないし、そういうことができる時代になってきました。今まで無駄な延命は止めましょう、ギアチェンジして緩和に入りましょう、とよく言われていました。最近は、その“無駄な延命治療”という言葉から“無駄”という言葉もはずされて、延命治療そのものがいけないように言われています」(「α通信」45号より 平成20年1月16日)。
緩和医療は自宅でも施設でも病院でも、その人らしく最期までくらすことを支えるもの。病気があろうと、障害があろうと、それと共になるべくこの世でのいのちをクオリティよく延命しよう。誰にでも寿命はあるが、与えられた寿命を精一杯生きようとする。だから医療は延命治療でいいのだと述べられたのです。終末期医療から出発した伊藤医師は「今は誤解を恐れずに言えば」と前置きしながらも「緩和医療をしっかりとやると延命になる。そういう緩和医療をやりたい」というのです。
こうした主張を正面から掲げた緩和医療医にであったのははじめてのことでした。緩和医療が治療体系のなかに入ったことはたしかです。これは、今回紹介があった東大のアンケート調査結果を見ても、「緩和ケアの段階になった進行がんの患者8割が、治る積極的な治療を望んでいる」という状況に、しっかり応えようという医師の力強いメッセージになっているのがわかります。
これに対して、医療者の8割は「緩和治療で安楽に過ごしたほうがベター」と考えています。この認識のギャップはいったいどういうことでしょうか。これまでの症例実績とエビデンスから「何が一番患者にとって楽な最期の過程かをわかっている」、そういう答えになっています。患者の切実な思いによりそう接点、ケアの視点がまったくといってもいいほど見えません。患者と医療者との乖離、これが緩和ケア病棟の現実なんですね。
患者中心といいますが、本来病院施設は医師がいて看護師がいてそこの患者が入っていく構図なんですから、主体は患者本人にはないのです。ここまで記述して、気づくことがあります。かつては緩和医療を支えていた理念的な支柱だった〈ホスピス〉ということばが、緩和ケア・マニュアルのなかに吸収されて死語になっていることと関係しているようにおもいます。患者にとっては基幹病院(がんセンター)、有床診療所、在宅医というラインだけが提示されています。
これにたいして在宅医として内藤いづみさんは、「治って、生き続けたい、あきらめたくない」と強く願っている患者の心身の苦痛の緩和につとめながら、ときには家族の声を聞き続けることがホスピスケアの大きな仕事の一つだと、ありました。これは病院の外へ、医療の外へでたときに見えるたしかなホスピス活動といえますね。
その通りだとおもいますが、いづみさんにはもうひとつホスピス医としての眼差し、つまり終末期の葛藤をいのちの臨界として受けとめようとしているところが画期的なところです。
臨界のイメージについてはある対談で「赤ちゃんを産むときには、これが臨界点、これを超えたら出産というのがありますね。それと同じで、ぎりぎりまで生ききると、これ以上は生きられないという臨界点があるようにおもいます」と語っていましたね。
ホスピスケアがいのちのケアにほかならないことをおしえてもらったのです。生誕と死は同じ位相と場所で起きる異なるいのちの出来事としてみているのです。産まれることと死ぬことが、(いのちの)臨界点ということばで一つになっていることです。第三者がわりこむことができない場面に呼吸をととのえて寄りそうことしかできない。またそれができる人だけがホスピス医になるのだろう。そう思います。
医師ではないわたしがそうした状況においこまれたときのケアのかたちを体験的にファミリー・トライアングルと呼んできました。義母の寝たきり状態のケアに際して考えた構図でした。義母と娘(妻)との関係にわって入るのではなく、3人目の位置に着く。そのかたちがサポートになるという考え方です。介護される本人がいて、家族なり、医師・看護師なり、本人を支えるひとがいる。それぞれが対等な関係で支えあって三角形を形づくっている。このトライアングルのポイントは介護される本人があくまで中心ということです。寄りそう際には軸になる3人目、3番目の位置と役割につくということです。前回紹介したタキさんとのおつきあい関係もこの位置取りでなりたっています。
いいかえれば3人目が想定できないケアはどこかで限界がくるのです。なぜなら、直接支えようとしている(二人目の)ケアギバーを励まし助ける力でもあるからです。ちなみにボランティアの役割もこの3人目の役割です。その自覚がないと関係を壊すだけになってしまいます。
今回、紹介された「森のイスキア」の佐藤初女さんもまた、ご自身の居場所や役割を自覚された方ですね。迷い、悩み、救いを求めて訪れる見知らぬ人と手作りのおむすびを供しながら寄りそう姿は、わたしも以前に映画『地球交響曲第二番』でその姿ふるまいから共感したことを憶えています。妻も「私は一度も減塩などしたことはありません。塩は人間の強いからだとこころをつくるのに欠かせない」いう佐藤初女さんのことばに、同士を得たかのような喜び顔をしていました。また、三度目のがん治療の療養中の女性は「佐藤初女さんに食はいのちとつながっていることをおそわった。もし胃瘻にしてはというはなしになったら、辞退しようね」と連れ合いに同意をもとめたそうです。
あらためてその力に思い知らされたことがあります。実は今年で4年目に入ろうかというおにぎりゼミ(大和市)を続けています。毎月第4金曜日夕方6時半から。参加者みんなで、こぶに鮭にたらこ等のおにぎりをつくりみそ汁を添えて、食しながら「今月のわたし、今日のきもち」などを語りあいます。ゼミが終わってから食すのではなく、食しながらはじめるのです。参加者の多くがいろいろな喪失体験をした人たちだということもありますが、食べて話して和んだところで用意したレジュメをだしての勉強会。こんな形式がすっかり定着していました。気づきませんでしたが佐藤初女さんの「おむすびの祈り」とどこかで重なっているかもしれません。
とはいっても病める人にとってお医者さんは、いるだけで安心できて信頼の対象足りうる存在であることはまちがいありません。患者のからだにそっとふれ寄りそって傾聴する姿…。先に話題になったテレビドラマ『風のガーデン』のなかでも老在宅医の緒形拳の背には紛れもなくホスピス医の姿が投影されていましたね。
さて、今回はもうひとつお答えしなければいけないことがありますね。
〈「治らない病気である」と受け入れても死にたくない、明日も生きたいという患者の生への執着。「治って生き続けたい、あきらめたくない」という強い願望〉という人のすがた・かたちは、エリザベス・キューブラー・ロスが「死の過程」の最後の段階として示した「(死の)受容」とずいぶんちがうのではないか、という指摘についてです。「納得して死を受け入れるということではなかったのか」という問い直し方ができるかです。
たしかに、死の臨床に立ち会った人のなかには「死を受容している人はいない」とエリザベス・キューブラー・ロスの理論を否定的にとらえている人がいます。そのことを確かめる手だては本人に聴く以外ありませんが、最晩年の著作『ライフ・レッスン』のなかにその返事があるのです。
ロスはここで、「死に直面している人たちはいつも、大いなるレッスンをもたらす教師だった。生がもっともはっきりみえるのは、死の淵に追いやられたそのときからだ。そのレッスンの数々は、人間の生にかんする究極の真実であり、いのちそのものの秘密である」といっています。そしてこの著作はロスの脳卒中体験とその後の介護をうけた経験等を踏まえて語られていることも忘れてはならないとおもいます。
そこでは「愛のレッスン」「喪失のレッスン」「怒りのレッスン」など人生の15のレッスンが採りあげられていますが、ロスの論点からいえば当然「受容のレッスン」があるはずですがさがしてもありません。このことに着目して私が受け取ったのは「明け渡しのレッスン」と「許しのレッスン」の中身でした。
このなかに「受容」の本意が語られている、そのように読むことができたからです。ポイントになるとおもわれる箇所をあげてみます。(傍線は米沢)
〈明け渡しと降伏には大きなちがいがある。降伏とは、たとえば致命的な病気の診断をうけたときに、両手をあげて「もうだめだ。これでおしまいだ!」ということだ。しかし、自分を明け渡すことは、いいとおもった治療を積極的に選び、もしそれがどうしても無効だとわかったとき、大いなるものに身をゆだねる道を選ぶことである。降伏するとき、われわれは自分の人生を否定する。明け渡すとき、われわれはあるがままの人生を受け入れる。病気の犠牲者になることは降伏することである。しかし、どんな状況にあっても、つねに選ぶことができるのが明け渡しなのだ。状況から逃げ出すのが降伏であり、状況のただなかに身をすてるのが明け渡しである。〉
〈死の床にある人たちは、ほんとうの許しについてたくさんのことを教えてくれている。かれらはけっして「おれはずっと正しかったし、いまもぜったい正しい。おまえがいかにまちがっているかは、おれがいちばんよく知っている。だが、寛大なおれは、おまえを許してやろう」などとはおもわない。かれらはこうおもっている。「おまえは過ちを犯し、おれも過ちを犯してきた。過ちを犯さない人なんていないんだ。でも、もうおまえを「過ちを犯した人」という目でみたくない。自分にたいしても、そんな目でみるのはやめた」〉
ここには、かつての5段階の最期の「受容(の葛藤)」が実は「明け渡し」と「許し」の表現までひらかれていることがわかります。いいかえれば、この明け渡しと許しが「受容」の真意と深さを伝えている、おしえてくれているのではないかということです。
エリザベスは若き日の処女作『死ぬ瞬間』では「受容」としました。その内実がよく見えないままに。それは死の過程を往路の眼差しからとらえたことばだったといえます。けれど、自らのいのちが還りのステージに入ったときの著作『ライフ・レッスン』では、自らの忍耐と経験を重ねて「受容」の内実を「明け渡す」という成熟した表現に置きかえられたのだと考えることができます。いのちを・人生を明け渡すこと、そこから先は自ずと彼岸(死)へのバトンリレーとして理解できますし、自然な感じがします。
「安心できないとき、それが明け渡すときだ」
「行きづまったとき、それが明け渡すときだ」
「自分はすべてに責任があると感じたとき、それが明け渡すときだ」
「変えられないことを変えたいとおもったとき、それが明け渡すときだ」
ここで「明け渡す」っていう箇所を「受容する」に置きかえてみると、それぞれがとても重い深いことばに変容することがわかります。ロスは晩年すごいステージにのぼりつめたのだ、そうおもいます。
※
今朝ほど、まつおかさわこさんのたしかな色彩と輪郭につつまれたメッセージ絵本『しあわせの13粒』落掌しました。すぐにも届けてあげたい人のかおが浮かびました。