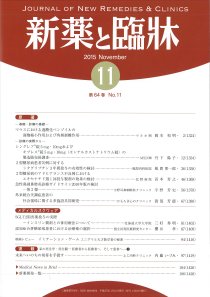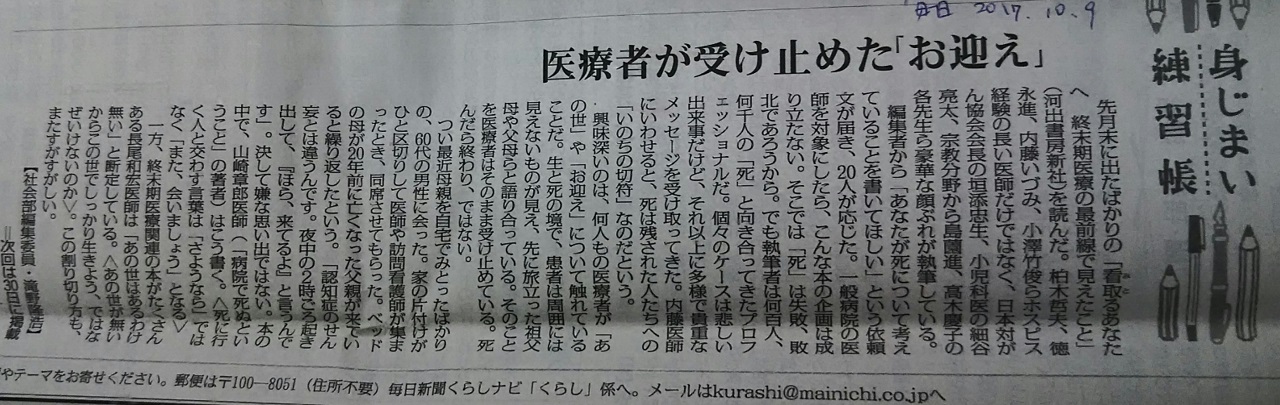最期のときを家族と
人間の尊厳とホスピスケア
80年代後半、英国に暮らし、ホスピスでボランティア医師として働いた。その体験を日本で伝え始めて20年近くがたつ。当初は理解してくれる医療者(特に医師)が少なかったが、患者さんと家族は、私の講演翌日に外来を訪ねてくることも珍しくなかった。当時、がん患者は病名を知らされないまま、病院で点滴につながれ、痛みの中で逝くのが一般的だったからだ。
46歳の渡井勝さん=仮名=は16年前、帰国後の私にホスピスケアを望んだ最初の患者さんだ。初対面の日、少し神経質な顔でこう切り出した。
「先生の講演を聞いて、がんの痛みは取ってもらえそうだと安心しました。病気の仲間は見ていられないほどの痛みにもだえ苦しみ、残された時間を家族と暮らすこともできずに死んでいきました。痛みは取ってくださいね。そして、病気が進んでも、僕にうそをつかず、病状を話してください」
「でも、それは、場合によってはかなりつらいと思います」
「分かっています。でも、知らなければ、自分で考えることも、選ぶこともできません」
「直腸がんが肺に1カ所小さく転移したのですね。外科医は肺の手術を勧めたのでは?」
「そうです。しかし、僕はもう手術も入院もしたくない。これまでたくさん治療を受け、長く入院生活を送ってきました。残された人生は愛する家族と暮らしたい。それが僕の選択です」
そう言って、ほっとした表情になった渡井さんを思いだす。
がんの痛みを緩和して穏やかに過ごす間に、渡井さんは静かに、着実に亡き後の支度を進めた。10代の娘2人の未来の設計図。妻の経済的自立への計画。そして、安定した日々はついに脳転移という事実で破られた。約束を守るときがきた。「残念ながら脳に転移しています。手術はできませんが、苦しみは最期まで緩和できます」
「先生、教えてくれてありがとう」。渡井さんは、私に笑顔を向けてくださった。
上智大学のアルフォンス・デーケン名誉教授は「人間の尊厳とは、自分で考える、選ぶ、愛することができること」と教えてくださった。日本の医療、福祉、教育の場で私たちは尊厳を貫き通しているだろうか?
2008年9月24日 産経新聞より抜粋