産声をあげるとき、息を引き取るとき
いきいき2013年6月号より、連載第二回目。
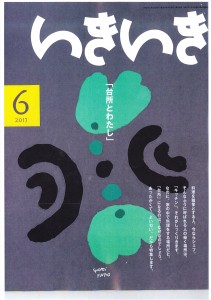
前回は、限られた時間4 過ごす人、それを見送る人へのメッセージをくださった内藤いづみさん。3回連続の2回目は、在宅ホスピス医としての原点について。
私は3人の子どもの母です。去年、未娘が大学生になり、家を出ました。この頃ようやく、子どものいない、夫とふたりきりの静かすぎる生活に慣れてきたところです。
ちょっと変に聞こえるかもしれませんが、子育てとホスピスケアは似ているなあと思うのです。何人育てても、何人を看取っても「慣れる」ということは決してない。その都度真剣勝負で、「こうすればいい」というマニュアルは一切ありません。
そして、産声をあげるときと息を引き取るときの状況も実はよく似ています。長野県松本市で聞かれた講演会でのことでした。このとき一本のDVDを会場のみなさんにお見せしました。ひとりのおばあちゃんが息を引き取る瞬間の映像です。
おばあちゃんは呼吸の間隔が3秒、4秒と長くなり、口は大きく開いたまま。意識はもうありません。いびきのような、カラカラと響く音を立てています。家族や親戚がおばあちゃんのベッドをぐるりと囲み「おばあちゃん、がんばれー」「ありがとう、ありがとう」と声をかけながら、涙をいっぱい浮かべておばあちゃんの顔や頭、体をさすっています。
生まれるときは、自分が泣いて、死ぬときは、周りが泣いて。
上映後、会場にいた妊婦さんが私のところへ来て、「先生、看取りの瞬間って、お産のときと似ていますね」と言いました。「みんなで体をさすって、『もうちょっとだ』『がんばれ』つて声をかける。あれは出産のときと同じですよ」と。
たしかにそのとおり。おもしろいなあと思います。生と死は、コインの表裏のようなもの。
以前、作家の遠藤周作先生からいただいた『チベット死者の書』を思い出しました。これは、死の瞬間から次の生を得て誕生するまでに魂かたどる四十九日の旅を描写した経典で、臨終を迎えた人の枕元で憎が読む習慣がチベットにはあるのだそうです。
経典には、「私たちが泣きながら生まれてくるとき、周囲の人々は歓喜の声をあげる。私たちが死んでいくとき、周囲の人々は泣き、私たちは歓喜に満ちて笑う」と書かれていました。
私の患者さんの多くは、亡くなって30分くらい経つと、穏やかないい笑顔になります。
その顔を見ていると、「ああ、いいところに行ったんだなあ」と、こちらもほっとした気持ちになる。あっちの世界々は怖いところではなさそうだ、と思わせていただいています。
自分の人生の締めくくりは自分で決めたい、という思い
私は、大学病院に勤務した後、29歳で。「ホスピス発祥の地」イギリスヘ渡り、ホスピスケアの基礎を学びました。大学時代に福島県で知り合って結婚したイギリス人の夫の、本社への異動が大きなタイミングとなり、いのちの主人公である患者本位のケアは何かを、本場で学ぶことになったのです。
大学病院勤務時代に感じていたのは、苦しみや痛みを訴えるがん患者さんに、信頼関係をもとにした満足な治療ができていない自分へのふがいなさでした。主治医でも、教授の許可がないと患者を退院させられない。
告知もできない。そこから生じる患者さんとの、本音ではないぎこちないやりとり。このままでいいのかと、いつも自分に問いかけていました。
そんなときに出会ったのが、23歳の女性でした。大学院生で、がんが肺に転移し、余命は4か月。私は彼女の主治医ではなかったけれど、同年代だったこともあり、毎日病室に足を運んで映画の話、恋の話などあれこれ語り合いました。賢い彼女は、告知されずとも自分ががんだとわかっていました。私は助かる見込みのない彼女に何かしてあげたいと思うようになりました。そしてついに「家へ帰りたい?」と尋ねてしまったのです。
「帰りたい」。彼女ははっきりそう言いました。「整理しておきたいものもあるんです」。彼女の望みは、チューブでっつながれた、スパゲティ状態の延命措置ではなかったのです。
自分の人生の締めくくりとして自分で余生を決めたいという強い思いでした。
「私か責任をもつ」と宣言し、私はご両親と病院の許可を得て、彼女を退院させました。まだ日本では在宅ケアがほとんどされていなかった時代。でも、ただ彼女が残された時間を穏やかに過ごせるように、それだけを願い、大学病院には内緒で往診を続けました。
彼女は自宅で家族とともに、普通の日常を送りました。「子どもを産んでみたいな」と夢を語ることもありました。「お父さんが毎晩顔をのぞきに来るの。息をしていないとでも思ったのかしら」。こちらに気を使わせまいと気丈にそんな冗談を言うこともありましたが、あとから聞いた話では、これまでつけてきた日記の始末をひそかにしていたのだそうです。
そして4か月後、彼女は大好きなお母さんに背中をさすられながら、その腕の中で息を引き取りました。
ご両親は、私に彼女の遺影を選ばせてくださいました。
私は家に帰ってから泣いて泣いて、ひとりで抱えるにはあまりにも重い仕事を選んだのだと、心から思い知りました。
彼女は生前、「大学病院の先生が100入いなくてもいい。内藤先生かいてくれるから。家で私を診てくれるから」と言ってくれました。その言葉が、どれだけ今の私の支えとなり、力となっていることか。彼女との日々が、私の在宅ホスピスケアの学びの旅の始まりとなりました。
学びの旅の舞台はイギリスーグラスゴーのホスピスヘと移りました。私か学んだところは、入院・通院・在宅の3タイプの中から、自分が望む方法を選べるというシステム。私はここで頭をガツンと殴られたようなカルチャーショックを受けました。末期がんで死期が迫った患者さんが、みんなニコニコと、とにかく明るく過ごしていたのですから。
全身にがんが転移し、食事をとることが困難になった通院患者の60代の女性に点滴をするよう勧めると「3時間もベッドにつながれているより、たとえひと口しか食べられなくても家族と食卓を囲み、みんなの笑顔を見ていたいの」とはっきりと断わられました。そして笑顔で食卓について、わずかひとさじのビーフシチューを口に運び、ゆっくりと味わった。
「死は敗北だ」という空気が充満していた当時の日本の医療現場では、まったく考えられない世界でした。
「ホスピスでベイビーの声が聞けるなんて」
さらに驚いたのは、私の子どもと患者さんたちとのことです。私はイギリスで二人の子どもを助産師さんに取り上げてもらいました。だから、イギリスでのいのちの始まりと最期のケアの手厚さがよくわかります。
一人目の長男を出産し、1か月半ほどたった頃、ホスピスの女性院長が「ホスピスにベイビーを連れて来てよ」とおっしゃるのです。恐る恐る行ってみると患者さんがあっという間に「おぎゃー」と泣く長男のところへ集まってきました。そして、「ホスピスでベイビーの声が聞けるなんて!」と細くなった腕を伸ばし、みなさん長男をいとおしそうになでてくれたのです。
「ベイビーがいるから来た」と言い、ホスピスに通っていた70代の腎臓がんの男性。衰弱して歩行も難しくなった時点で在宅ケアを選択されましたが、私が長男と往診に行くと、目を輝かせて体を起こし、「おおベイビー、よく来たねえ」と、とても元気になるのです。枕元の自分の息子の写真の隣には、最期まで私の長男とのツーショツトを飾ってくださっていました。
子どもを見て、連綿と続くいのちのエネルギーを予感する。
死生学を専門とする上智大学名誉教授のアルフォンスーデーケン氏は、以前私に「お年寄りは泣いている子どもを見て、自分の消えゆくいのちを悲観するのではなく、連綿と続くいのちのエネルギーを予感して、子どもからエネルギーを受け取る。子どもは老いの姿に日常的に接することがデス・エデュケーションになる」とおっしゃいました。デス・エデュケーションとは、死への心の準備をする教育のこと。イギリスのホスピスで私か見たのは、まさにお年寄りが赤ん坊からエネルギーを受け取る瞬間だったのです。
帰国後、私が看取った患者さんの中に、小学生のお孫さんと同居する60代の乳がんの女性がいたのを思い出します。この女性が亡くなってから数年後、ふと朝刊をめくっていると、高校2年になったあのお孫さんの作文が入選し、紹介されていました。作文は、おばあちゃんとの最期の日々を綴ったもので、「祖母は弱っていく自分を受け入れ、死に向かっていくことを理解し、最期までたくましく生きていた」とありました。
戦前はほとんど自宅だった出産も看取りも、今は病院という隔離された場所で扱われることが一般的になり、いのちのリアリティーが、違い存在になったように思います。人は必ず死ぬ。でもそのいのちは紡がれる。
いのちに向き合うことは、豊かに生き、豊かな社会にするために大事なことなのだと、あの作文は改めて思い知らせてくれたのです。

