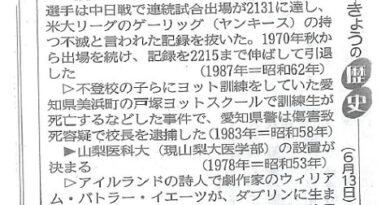死ぬなら自分の家の畳の上でがんばらないけどあきらめない
死ぬなら自分の家の畳の上でがんばらないけどあきらめないby 鎌田實
週刊朝日2005・12・30号より
怪人二十面相のような魅力的女性。なんだか、女性への誉め言葉にならないけど、とにかく色々な顔をもった美しい女性なのだ。
山梨県の教育委員長をしている。偉いのだ。3人の子どものお母さん。肝っ玉母さんなんです。イギリス人の夫の妻。なんでもできるやさしい夫。夫に恵まれている妻なのだ。幸せ者ということ。全国から声のかかる命の講演会は絶品。次々に命の本を出版する。11月にも新刊が出た。あなたが、いてくれる。(佼成出版社)。これから売れる作家なのだ。在宅ホスピスの専門 医。今が旬。
いづみファンは多い。永六輔、遠藤順子、柳田邦男、ピーコ……かくいう私も。みんな内藤いづみに最期を看とってもらいたいと思っているのかもしれない。がんの患者さんが具合悪いと、夜中でも往診してくれる。時には、すぐ に飛び出せるようにジャージを着て眠っている。全力投球だ。
在宅ホスピスの専門医って、なんだかわからないかもしれない。もっとわかり易く言うと、自宅にいたいと思うターミナル・ステージのがん患者さんの希望をかなえてくれる医者。アンケート調査によると、6剖の人が自分の家の畳の上で、苦しまずに、死にたいと希望している。大好きな自宅で、限られた時間をその人らしく生きるのを応援してくれる医者。痛みや苦しみをとり除いてくれるプロフェッショナル。いづみ先生なら、最後の最後まで意識がはっきりしていて、痛みをピタッと止めてくれる。
日本の医師は患者さんの痛みに鈍感だ。患者さんが「痛い」と訴えると、「がまん・がまん」とか「痛くない・痛くない」なんて平気で言う。
もっとひどい医者がいた。
病院での緊急処置が必要だったので、救急車に同乗して、それまで、がんの治療をしていた病院に付き添った。担当医は本人の聞こえる前で、「末期の人に何をしても無駄です。
ここに来てもすることはない」と冷たく言った。いづみ先生は冷たい医療に黙っていない。闘う。死にゆく人を最期の瞬間まで、一人の人間として尊重したいと内藤いづみは思っている。
がんの痛みに対して、我慢なんか、いいことはこれっぽつちもない。世界保健機関(WHO)が「WHO方式がん疼痛治療法」のガイドラインを発表している。
痛みの強さに応じた薬を使う。
痛みが強ければれば、最初からモルヒネを使ってよい。
日本人にはここで、誤った思い込みがある。一つは麻薬を使うから、もう終わりだと思いがち。そうではない。早期がんでも、痛みが強いこともある。その時、痛みをとりとり除いてあげると食欲もでて、元気になり、病気の勢いをとめることができる。次の先入観は、モルヒネは麻薬なので依存症になるのではと心配する。研究の結果、がんの痛みに対して、適正な料のモルヒネを長期間使用しても、精神的な依存はおこらないことがわかっている。
国際麻薬統制委員会の2001年のデータによると、100万人に対して、一日のモルヒネの消費量(グラム)は、カナダ135・5、オーストラリア31・1、フランスが87・0、米国が85・3と高いのに、日本は19・8と先進国のなかでは極端に低い。
日本では、痛みを我慢させられている患者さんが、いかに多いかという不名誉な結果だ。
こんな死に方してみたい医療用モルヒネの使用量と、その国の文化水準は正比例するという学者もいる。日本は文化の後進国なのかもしれな い。
日本で、やっと使用量が増加する傾向が最近見られる。
代診を置いて、いづみ先生が日本中を啓蒙して歩いている
成果かもしれない。
いよいよという状態の時、いい子を演じなくていい。せめて、痛みだけはしっかり止めてと、病院に要求していい。
がんばらなくていい。腕のいい緩和ケア医なら、トータルペインの緩和をしてくれる。
体の痛みだけでなぐ、心の痛みも、社会的な痛みもとり除いてくれる。さらにスピリチュアルな痛み、この世からいなくなる不安など、言葉に表しにくい痛みも緩和してくれ る。
ある時、スイミングスクールのインストラクターが、がんの末期になった。彼は最後まで水に触れていたかった。
いづみ先生は、水着になって患者さんから水泳を教えてもらうことを通して、患者さんの心をつかんだ。支えてもらうだけでなく、主治医を指導した患者さんは、なによりもの生きる力をもらった。
賭け事の好きな患者さんが、がんの末期になった。自宅で、最期まで競馬をやれるようにしてあげた。大穴を当てた。
その人がその人らしく生きることをモットーに最後まで、いづみ先生はていねいに支える。体の痛みだけでなく、心の痛みにも心を配る。
「こんなドクターの近くに住んだら、人生の最終章が豊かになるだろう」と柳田邦男さんが語っている。その通りだと、ぼくも思った。