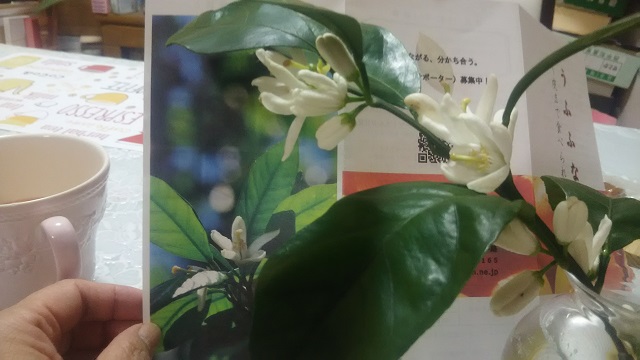遺稿集が発行されました
村石保さんは、深いご縁をくださった編集者です。
わたしの代表作、「あした野原に出てみよう」を産み出してくれた人です。一年前にお亡くなりになりました。
奥さまの純子さんが、彼が病床で書き続けたブログを本にして発行されました。
何という素晴らしい同志でしょうか。
私は旅立ちの様子を前書き(↓「村石保さんと出会って」)に書かせてもらいました。
ちなみに本のタイトルの「待庵(たいあん)」、について。
ご本人が本のなかでふれていますが、
『茶道をかじったものなら知っている、千利休さんがお造りになった究極の二畳の狭さの茶室のこと』
です。現存保存されています。
村石さんが病室のベッドに横たわり、見あげた天井が二畳ほど。そこから待庵を思い浮かべたそうです。待庵から広がる彼の宇宙を思います。
それにしても、もう一年もたってしまったのだと、思い出がよみがえります。
村石保さんと出会って
季節はめぐる。今年の桜はずいぶんと早く咲いた。私は風に散る桜の花びらが好きだ。その花ふぶきのなかにたたずみ、旅立った親しい人を思い出している。
この本を手にしているどなたにも、村石保さんとの出会いがあり、彼がどういう人であるか十分わかっているだろうから、改めてここでのべるつもりはない。どなたも、この時代のどこかで、彼に出会えたことの幸運をかみしめていらっしゃると思う。
私は20年ほど前に彼に出会えた。数年くらした英国から家族とともにふるさとの山梨県甲府市にもどり「ホスピスケア」という人生の最終章の選択肢について社会に伝え始めた。当時の日本ではあまり知られていない新分野のホスピスケアは、医療活動でありながら、「生と死」を考える社会の成熟度と文化力を反映するものだった。
医療界では通常あるように、権威ある組織の一員として、下積みからコツコツと積み上げていくという方法(しきたり)を私は無視した。あまりにその構造は古くさくて膠着していたから。講演活動などで、直接当事者たち(患者さんや家族)に伝えるという方法をとった。メディアにも多くとりあげられた。
「いのちの主人公が決めていいのです(チョイス イズ ユアーズ)。本人が情報を得ること。いのちの最終章を支える方法(ホスピスケア)があります。」
それは若さゆえのエネルギーに満ちた声だったと思う。しかし突然のそんな声に大先輩たちからは反発を招いた。いじめる人がいれば、助けてくれる人もいる。突進する私を見守り応援してくださる方々も出てきた。
茅野市で地域医療活動を広げる鎌田實医師、松本市で古いやり方と戦う坊さん高橋卓志さん。このお二人と私で鼎談をすることになった。わがままでマイペースな私たちの話しを、村石さんがすてきな本にまとめてくれた。『ホスピス最期の輝きのために』。その縁で『あした野原にでてみよう』という単著も誕生した。永遠の別れのあと、どんなに悲しくても、どんなにつらくても、いつの日か自分を取り戻し、野原に出る日が来る。そんなメッセージが伝わる私の代表作となった。
「医者になって本も出版する。」それは14歳の私の夢だった。村石さんは私の夢をかなえてくれたのだ。その後も、いのちの学びをお互いに重ねながら、本の出版が続いた。私の家族とも交流して下さり、私の子どもたちは「森のやさしい哲人(考える人)」とひそかに呼んでいた。
晩年、彼は重い病を得て、積極的な治療を選びチャレンジした。コロナ禍だったから、入院してしまうと家族にも友人にも会えず、孤独の中で抗がん剤治療を受け続けた。そんな日々、病床で「書くこと」は彼の尊厳と生きる力を守ったのだろうと思う。治療は一進一退だった。
入院が長引いたある日、病床から電話がきた。
「いづみさん、おれ、これからどうなるんだろう?」
いつもの落ち着いた深い声色だった。
たくさんの末期がん患者の最期にかかわってきた医師の私だが、友人としてこう伝えた。
「村石さん、いつまでそこにいるの?治療はもうきりをつけてもいいのでは? 入院している限り、大切な奥さんや愛犬、友人にも会えないよ。まるで幽閉されている政治犯みたいだ。おい、政治犯、もう外に出ておいで」。
政治犯と聞いて彼は苦笑した。
「出たいよ、もちろん。これからおれは大丈夫かな?」
「大丈夫。ぼつぼつ生きていけばいいんだよ」
「そうか。怖くないね。ぼつぼつだね。」
「私も往診医を探してみるから」
そんな会話のあと事態は一気に進み、共通の知り合いの在宅ホスピス医が引き受けてくれることになり、彼は退院した。私もお見舞いすることを約束した。
彼は飯綱の森の中へ戻った。森の風に触れ、鳥の声を聴き、喜ぶ犬の頭を撫でた。妻の作るおいしい料理を食べ、友人たちの訪問が続いた。”ぼつぼつ“どころか大騒ぎの日々だったと思う。
ある明け方メールが入った。24時間出動する往診医の私は、枕もとの携帯電話の着信音ですぐ目が覚めた。
「村さん、もうあぶないかもしれない」。
妻の純子さんからのメールだった。
「えっ?もう危篤に?」
私の脈が速くなった。会うという約束が守れないなんて嫌だ。
甲府から電車を乗り継いで向かうことにした。生きている間に会えないかもしれない、と内心思った。
在宅ホスピスケアの現場では、私はチームのリーダーだから、泣くことは許されない。全てのエネルギーは患者さんの安らかな旅立ちにかける。責任は重い。泣いているひまはない。でも、友人の危篤の枕元ではワンワンと泣くことは許されるだろうと思い、ポケットにハンカチをたくさん詰め込んだ。
甲府からの旅路は遠かった。やっと山荘の入口にたどりついた。「まだ、息はあるだろうか?」と私はドキドキして玄関のドアを開けた。
「遅くなってごめんなさい!」
まだ、息はあった。でも苦しそうな声が出ていた。私ならもう少し楽にしてあげられるかも。ここで役に立てなかったら、在宅ホスピス医・内藤いづみと知り合った意味がない⁈
私はドタドタとベッドサイドに駆け寄った。どんな最期の時間でも、その人の役に立つことは残されている。
昔のお産婆(さんば)さんだったら、たすきをかけて気合を入れて妊婦に向き合うだろうな(私もたすきがほしい!)。そんな気持ちが湧いた。いのちの始まりと最期のケアは、実は似ている。
「私、お産婆さんなんだよ、村石さん。私といっしょにいのちの本をたくさん作ってくれたあなたならわかるよね?こちらへやってくる時のお手伝い、あちらの世界へここから飛び出す時のお手伝い。どちらも誕生なんだと思う。」と村石さんに心の中で話した。
関わってくださっている在宅医に電話をかけ、このステージで横から手を出す非礼を詫びた。そして、私が使いたい薬を持ってきてくれるよう頼んだ。その医師は快く了解してくれた。
こうして村石さんの状況は私の目から見て少し安穏になった。私は耳元で声をかけた。
「今まで、文句も言わず治療よくがんばったね。偉いよ。こうして家に戻れてよかった。好きな人たちも周りにいるよ。私の友人でいてくれてありがとう。もういいね。向こうに行こう。向こうに飛び出す扉を開けていいよ。どんな世界なんだろう? 光に満ちた世界かな?」
純子さんには「これからが人生最後の最大の仕事です」と伝えた。純子さんの腹が据わった。彼女も心の中でたすきをかけたのか、きりりとした表情になった。
悲しみにくれる見舞客たちに大声で伝えた。
「これから村さんは人生最大の大仕事に取り組みます。励ます人は残って。泣く人は帰ってください。」
さすがに村石さんが選んだ女性だ。彼はいつも彼女の胆力を誇りにしていた。
みんなで向こうに旅立つ村さんを応援し、見守った。そして、夜を越えて彼は昇天した。自分で選んで(チョイス イズ ユアーズ)彼は見事に輝くいのちを燃やし尽くして旅立った。
一年後、野原に立った純子さんは、こうしてすばらしい本を創った。最高のパートナーだ。村石さんはどんなに喜んでいることだろう。この混乱する世界であなたに出会えた誰もが、思い出とともに生きる力を与えられている。いのちのブライドがピカピカ光っている。
本当にありがとう。村石保さん、私たちもその日まで生き抜いていくよ。