「死」は、生きることに組み込まれている。
月刊「潮」2022年8月号、「連載 鎌田實の『希望・日本』」より。

生きているってこういうこと?
社会の混迷が深まるいま、改めて実感していることがある。それは命の大切さについてだ。パンデミックによって多くの人々が命を落とし、ロシアによるウクライナ侵攻では罪のない大勢の一般人が亡くなっている。いったい誰がこんな二一世紀を予想しただろうか――。
そんななか、今年の二月に一冊の対談本が刊行された。タイトルは『人間が生きているってこういうことかしら?』。著者は、ゲノム研究から三八億年の生命のつながりを見つめてきた生命誌研究者の中村桂子先生と、山梨県で四〇〇〇人以上の患者さんの命に寄り添ってきた在宅ホスピス医の内藤いづみ先生だ。
本書では、僕が昔からよく知るお二人が、それぞれの立場からさまざまな角度で〝命〟について語り合っている。読み終わると、なんだか直接お話を聞きたくなったので連絡をしたところ、お二人とも快諾してくださった。
初めにうかがったのは、本のタイトルについて。対談を行って、原稿にまとめたあとに編集者が提案してきたのは「生きているって〝どういうこと〟かしら?」というタイトルだったそうだ。これについて、内藤先生は「最終的には中村先生のご意見がビシッと通ったんです」と振り返る。まずは中村先生に、その意見について聞いてみた。
「〝どういうことかしら?〟って問いはとても大事なんですけど、私たち年長者の役割としては、この歳まで生きてきたんだから〝こういうことかしら?〟って言ってしまってもいいんじゃないかと思ったんです。どれも小さな体験ですし、ときどき間違うかもしれないんですけど、〝こういうことかしら?〟というのが、いまの私の率直な気持ちなんです」
先述のとおり、中村先生は長年にわたってゲノム研究に従事してきた生命誌研究家だ。「生命誌」とは、ひとことで言えば生命の歴史物語を読みとること。中村先生の専門性を理解しておくために、僕もあまり区別がついていなかった「遺伝子」と「DNA」と「ゲノム」がそれぞれ何を意味するのかをうかがった。
「DNAはデオキシリボ核酸の略だから、モノの名前です。これが遺伝子としての大事な役割を果たします。他方、ゲノムは人間の細胞のなかに入っているすべてのDNAの塊のことを指します」
そう説明してくださったうえで「ぜひ皆さんに知っておいてほしいことがあるんです」と中村先生が話を続けてくれた。
「『遺伝子』という言葉は昔からあったし、『遺伝』という言葉については『親からの遺伝』といった感じで日常会話のなかでも使われてきました。ただし、遺伝子とは何かということが科学的に説明できるようになったのは、つい最近のことなんです。具体的には、一九五二年に行われたアメリカ人の遺伝学者であるハーシーとチェイスによる実験によって、遺伝子とは何かがわかったんです。
例えばウイルスの場合、DNAやRNAの外をタンパク質が包んでいます。構造的にはDNAやRNAよりもタンパク質の方が複雑ですので、実験以前は後者こそが遺伝子だと思われていました。ところが、細胞に感染させてみると、残ったのは単純な構造の前者でした。こうして遺伝子の正体がわかったのです。現代の人々はなんでも科学で説明がつくと思いがちですが、いまわかっていることは昔からすべてわかっていたわけではないのです」
DNAこそが遺伝子であり、その塊をゲノムと呼ぶ。ならば、ゲノムには全遺伝子が入っているのだから、人のすべてはゲノムによって決定付けられるのだろうか。そんなふうに考えてしまいたくなるが、それは大きな間違いだという。
「すべてが入っているものの、それだけでは人のすべては決まらないんです。ここが大事なポイントです。どんな環境で過ごしたのか。何を食べたのか。どんな空気を吸ったのか。どういう気持ちで過ごしたのか。そういったことこそが、人のすべてを決定づけるのです」
中村先生によると、認知症やがんはさまざまな遺伝子がかかわりあって出てくるという。また、認知症やがんにつながる遺伝子を持っていたとしても、引き金さえ引かれなければ発症しないまま人生をまっとうすることもできる。これは、僕が長らく続けてきた健康づくりの取り組みを裏付ける話でもある。つまり、引き金が引かれないようにするために、運動をしたり、野菜を食べたり、ストレスを溜めないようにしたりといったことが大切になるのだ。
ゲノムに時間を入れる
この対談本のひとつの特徴は、お二人の詩的な言葉遣いにある。例えば、僕がもっとも興味深いと思ったのは〝ゲノムに時間を入れる〟という表現だ。この意味について、中村先生に聞いてみた。
「科学の世界で求められているのは〝時間を切る〟ことですよね。時間を短縮したり、効率性を高めたり。ところがゲノムについて考えてみると、すべての生きものって三八億年前に誕生した祖先細胞から始まってるんです。鎌田先生の細胞のなかにあるゲノムはご両親から半分ずつ受け継いだもので、ご両親はそれぞれのご両親から半分ずつゲノムを受け継いでいる。それを辿っていくと、必ず生命の起源に辿り着きます。
例えば、鎌田先生のゲノムには三〇億年ほど前にバクテリアが手に入れたエネルギー生産のための遺伝子なんかも含まれているわけです。つまり、私たちの細胞には、三八億年という〝時間〟が入ってるんです。命の重みについて考えるときに、私はこの時間の重みがとても大きいはずだと思っています。すべての生き物の細胞のなかに三八億年の時間が入っているわけですから、人間の生命だけがとりわけ重いということにはなりませんよね。それぞれの生命が固有の重みを持っているんです」
お二人の対談は、この〝時間を入れる〟という言葉から大きく展開していく。面白いのは内藤先生の応答で、彼女は在宅で患者さんを診るという自身の立場から、医療にも〝時間を入れる〟ことで新しい視点が生まれるのではないかと語り始める。その点について、内藤先生はこんな話をしてくれた。
「いま、医療の世界にも時間の短縮という大きな流れがあります。入院の期間は以前よりも短くなっているし、在宅ホスピスケアの時間も短くなっているんです。昔だったら余命三ヶ月ほどで在宅に移っていたのが、いまは一週間とか二、三日とかで亡くなってしまうケースが増えています。在宅に切り替えて八時間後に亡くなったというケースもありました。
がん患者に関しては、治療が進化したためにギリギリまで選択肢があるんです。だから、直前まで抗がん剤治療をやっていたりするわけです。そうすると、患者さんは治療に集中するために寸前まで死を直視しないんですね。自分の人生に折り合いをつけるという発想にはいたらず、いわば自分自身の最大の悩みである死を直視しないようにしているんです。
それを患者本人が望んでいるのかというと、多くの方々は我慢しているように思います。私たちのようにサポートできる人間が近くにいれば、早めに在宅に切り替えるように背中を押してあげられるんですけどね」
僕はいまも諏訪中央病院の緩和ケア病棟で、月に一度か二度の頻度で回診している。内藤先生が言うように時間が短縮されてしまうと、患者やその家族と医療者の信頼関係を築くのが難しいだろうと思う。緩和ケアには、患者やその家族と医療者とのあいだに信頼関係が必須だ。
僕が話を聞いている限りでも、以前であれば理学療法士が入って在宅へ切り替える訓練をしたり、実際に在宅に切り替えたりしていたのが、いまは時間が短縮されてしまってその余裕さえない緩和ケア病棟が増えているという。内藤先生は、コロナ禍がそうした大きな流れに拍車をかけたと言う。
「病院やグループホームに入っている人の家族は、コロナ禍のなかではお見舞いすらできず、会えたとしても時間が限られてしまっていました。火葬場でも家族がそばにいられず、お骨になってようやく〝対面〟できるという状況さえありました。
よい看取りには時間がかかるんです。医療者としては、本人だけでなく家族と信頼関係を築いたり、家族の歴史に耳を傾けたり、診療室の机のうえだけで治療はできないんです。場合によっては患者さんのそばで一緒にお茶を飲んだり、認知症の患者の方に『あなた、ずっとそばにいてくれるけど本当にお医者さんなの?』と思われたり。コロナ禍のなかでは、そういう〝のりしろ〟が一気に狭くなってしまいました。時間の短縮が人間らしい看取りを阻害するということを、コロナ禍が浮き彫りにしたとも言えるはずです」
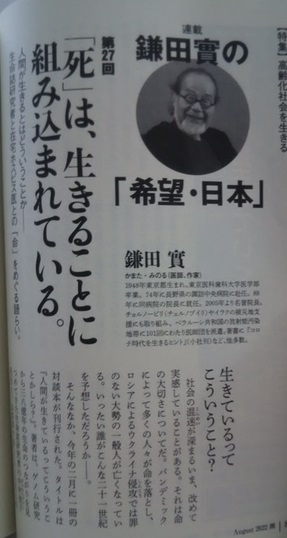
逝くときの時間は縮めてはならない
では、よい看取りとはどんなものなのか。内藤先生がご自身のお母さまを看取ったときの話がとても心に残った。看取ったのは特別養護老人ホーム。内藤先生が駆け付けたときには、すでに昏睡状態だったという。
「最期を考えたときに、口を聞けなくても味覚は残っているんじゃないかと思ったんです。それで、母は最後に何を口にしたいかと考えて、思い当たったのが日本酒だったんです。〝良妻賢母〟を美徳とした時代の人ですので、子供や夫の前では飲みませんでしたが、実は〝いける口〟だったんです。本当はお父さんよりも強かったんですね。
私はすぐに病院近くのコンビニに飛んでいき、カップ酒を買ってきました。ティッシュでこよりを作って、一滴だけ母の口に入れると、ゴクンと飲むんです。そして口を開くんですね。二滴、三滴と口に入れてあげるとまたゴクンと飲み込む。母はもう何も話せないのですが、最後の時間をそうやって過ごすうちに、話すよりも深く語り合っているような気がしました」
この話には後日談がある。次の日に、母親のもとに内藤先生の弟夫婦がやって来た。口の開いたカップ酒を見て、内藤先生は叱られたという。
「私の考え方をよく知っている弟だったんですけどね。だから、看取りの仕方については徹底的に話し合いました。気心が知れた姉弟同士でも、大切な母を看取る際にはすり合わせが大切なんです。そこにはやはり〝時間を入れる〟ことがとても大切だと思います。
人が誕生する際の妊娠からお産までは、一〇カ月という時間を短縮することができません。もしも医療の進歩によってその時間を縮める薬が出てきたら、それはとても怖いことですよ。同様に、人が逝くときの時間も縮めてはならないと思うんです」
僕にも内藤先生と同じような経験がある。父親の看取りのときに大好きだったビールを脱脂綿に含ませて数滴飲ませてあげたのだ。父親はいつもキリンビールを飲んでいたのだけど、なんとなく「最後なのだから」と、わざわざ陶器に入ったドイツのビールを用意した。父親は何も言わなかったのだけど、あとになって考えてみると「いつものビールを飲ませてくれよ」と思っていたのかもしれない。真意はわからないけれど、そのときのことを思い出すたびに、いまなお僕は父親と心のなかで対話を続けているような感覚を覚える。看取りに関しては、中村先生がこんな話をしてくれた。
「ある意味では、人間にとって最も大きな死は家族や友人などの身近な人の死だと思うんです。なぜなら、人間は自分自身の死を〝体験〟できないからです。意識がなくなってしまえば、自分の死と向き合うことはできないわけですから。
だから身近な人の死、すなわち〝二人称の死〟は自分自身にとっても大切なことなんです。ゆえに、医療者がそこに〝時間を入れる〟という感覚を持ってくだされば、それは本当に意味のあることだと思います。医療を受ける側からすれば、それこそが本当の医療の在り方だという考え方が広まってほしいですね」
“脱炭素”という言葉の違和感
もうひとつ、対談本のなかからお二人らしい詩的な言語感覚が表れている部分を紹介したい。それは、最近流行りの「脱炭素」という言葉に関する中村先生の考察だ。それについて、こんなふうに語ってくれた。
「〝脱炭素〟というのは、要するにCO2(二酸化炭素)を減らそうという話ですよね。炭素それ自体をなくそうという話ではない。それなのに〝脱炭素〟というのは言葉としておかしいと思っています。そもそも、二酸化炭素って炭素化合物のなかでは特別なものなんです。炭素は私たちの体のなかでお砂糖になったり、タンパク質になったり、さまざまな形で働いているんですけど、二酸化炭素になった場合は反応ができなくなるんです。それをもとに戻せるのは植物だけ。いわゆる光合成ですよね。炭素というのはそうやって循環しているのに〝脱炭素〟という言葉はそのダイナミックな営みを捨て去るような印象を持ちます。きっと、生き物離れをした技術の言葉なんでしょうね」
僕自身もそう言われてみて初めて「脱炭素」という言葉のおかしさに気が付いた。単に言葉が適切でないということだけではなく、その背景には生命観の乏しさがあるような気もしている。そんな現状に対して、中村先生は日常のなかで循環を実感することが大切だと指摘する。
「例えば調理の際に出た生ごみをそのまま燃えるゴミとして処分するのではなく、庭の落ち葉だめのなかで分解する。そうすると、想像以上に早く土に還るんです。そんな日常の小さなことを繰り返していると、おのずと生命の循環みたいなことを実感できるのではないでしょうか。なんでもかんでも社会のシステムに任せるのではなくて、生ごみくらいは自分の責任で分解してみる。高層マンションでは難しいかもしれませんが、一人一人がそうした小さなことに取り組むことでしか、生命観や死生観は変わっていかないと思いますね」
お二人に直接うかがってみたかったのは、彼女たち自身の死生観についてだった。特に〝死〟をどう捉えているか。内藤先生は〝死〟のイメージについて、次のように語る。
「母の最期のときに思ったんですけど、〝死〟の瞬間には生命が解体されて砂のような感じでワーッと宇宙の片隅に吸い込まれていくようなイメージなんです。生命の粒子が波とか雲とかみたいにワーッと。だから、私に〝死〟の瞬間が訪れてもあの世で母親に再会することはない。でも、母親の生命を構成していた粒子には会える。もしかしたら、私の粒子と母親の粒子の見分けがつかなくなるかもしれませんね。そこは生命の源のような場所で、粒子は大きな循環のなかに溶け込んでいく。そんなイメージを持っています」
なんとも内藤先生らしい言葉だと思った。一方の中村先生は、生命誌の観点からこんな話をしてくれた。
「私の頭のなかでは、生と死は対するものではないんですよね。なぜなら、生きることには死が組み込まれているからです。例えば、人の五本の指って、ある細胞が死ぬことによって出来上がるんですよね」
お二人には最後に、現下の世界情勢を踏まえて、いままさに考えていることについてうかがった。
「中村先生のお話を聞いて、生命誌の観点から見ればいま私たちがここに誕生していること自体が奇跡なんだと実感できました。だからこそ、すべての生命が天命をまっとうできるような環境をこの世界に築かないといけません。私は痛みを緩和する専門家なので、それが誰であろうと、どこの国の人であろうと、痛みを見るのは本当に辛いんです」(内藤先生)
「個の尊重は大切ですが、同じくらい〝私たち生き物のなかの私〟との自覚を持つことが大切だと思います。実は、ヒトゲノムを調べるときに議論が分かれたのは、いったい誰のゲノムを調べればヒトゲノムを調べたことになるのかという問いでした。
結論を言えば、誰を調べてもヒトゲノムなんです。典型的な人なんていないとも言えるし、誰しもが典型的とも言える。最終的にはさまざまな国の六人を調べることになりました。つまり、ゲノムのレベルでは私たちに大きな差はないわけです。ゆえに個の尊重とともに〝私たち生き物のなかの私〟との自覚が大切になるのです。その自覚があれば、いまのような分断は起きないはずです。ぜひとも、そうした生命観が基本的なものとなってほしいですね。そう願っています」(中村先生)
それぞれの立場から真摯に生命と向き合ってきたお二人の言葉には説得力がある。混迷を極める時代だからこそ、一人一人が生命についてより深く考えるべきなのだろう。

