インタビュー「住み慣れたわが家で、家族と共に最期の時を迎えたい」
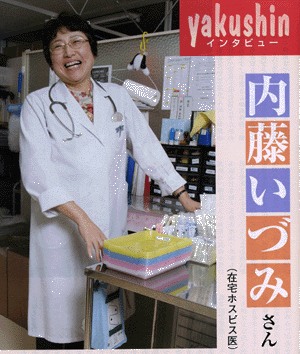
「住み慣れたわが家で、家族と共に最期の時を迎えたい」。末期がんと闘う人の思いに寄り添い、在宅での終末期医療に取り組む内藤いづみさん。在宅ホスピス医として、これまで多くの患者さんと向き合ってきた内藤さんは、「普段の日常のなかに、大きな幸せがあることを教わった」と語ります。真に豊かな人生とは何か。内藤さんにうかがいました。
幸福な時間を生みだす
在宅ホスピスで一番大切にされていることはなんですか?
在宅ホスピスとは、治癒の見込みのない末期がんの患者さんが、最期の日々を自宅で家族と共に過ごすための医療なんです。患者さんの肉体的、精神的苦痛を取り除き、ご家族と協力しながら、皆でその方のいのちの最期を看取る。そのなかで患者さんには、最期の瞬間まで可能な限り生きる希望や喜びを味わっていただき、またご家族には、いのちの尊さを自然にかみしめていただけるようケアすることを第一に考えています。
今は八十パーセントに近い人が病院で亡くなる時代です。この数字だけを見れば、多くの人が病院で医療を受けられる日本は、医療先進国なのかもしれません。しかし、いよいよ治療法がない、となった時、本当に幸せな最期を迎えられるかといえば、私には疑問が残ります。
がんの患者さんはこれまで、自分の症状をきちんと知らされないまま激痛に耐え、抗がん剤の副作用で食事が摂れなくなるなど、気力や体力をすっかり奪われてしまうことがありました。
痛みや不安が患者さんから理性を奪い、つい見舞いに来た家族に、当たり散らしてしまう。それで本人も家族も傷ついてしまうことが多いんですね。
もし、痛みを取り除くことができて、住み慣れたわが家で家族と過ごし、行きたいところへ出かけ、会いたい人に会うことができたら……。たとえ、それがほんの短い時間であっても、患者さんやご家族にとって、本当に濃密で大切な時間になると思うのです。在宅
ホスピスとは、そういう幸福な時問を生みだすお手伝いをする仕事なんです。
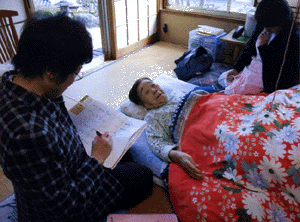
実際にはどのような医療行為をされるのですか?
ホスピス医療では、患者さんのトータルペイン(全人的な痛み)を嬢和することを考えます。患者さんの痛みには「体の痛み」のほかに、「心の痛み」「社会的な痛み」「霊的(スピリチュアな痛み)があるといわれます。「心の痛み」とは不安や恐れ、悲しみなどをいい、「社会的な痛み」とは、残された家族に対する心配や経済的な不安、働けなくなることへの挫折感など、社会的な存在として感じる痛みのことです。最後の「霊的な痛み」とは、「生きることの意味はなんだったのか」というような、人間存在の根本に関わるもので、「魂の痛み」と言い換えることができるかもしれません。
ホスピスではこの四つの痛みを取り除く必要があるとされていますが、「体の痛み」を緩和しなければ、患者さんは残りの問題にじっくりと向き合うことができなくなってしまいます。ですから、ホスピス医療ではまず、WHO(世界保健機関)のガイドラインにそって、患者さんの症状に合わせて鎮痛剤を投与していくのです。
体の痛みが緩和されれば、だれもが残りの問題にきちんと向き合えるのでしょうか?
患者さんは、痛みの原因であるがんを耽り除いているわけではないので、一度痛みを緩和しても、しばらくするとまた別の症状が出で、新たな痛みが生じてきます。その度にどの薬が効くのか、こちら側のカが試されている思いになります。でも、こうした繰り返しの中で死を深く見つめてきた患者さんは、不思議と顔が神々しくなるんですね。家族に支えられながらいつの時点でか、自分の我を捨てられ、すべてをゆだねるという気持ちを抱かれるようです。見守ってくれる愛する家族に、あるいはもっと大いなるものに...。
人間は大自然の一部として生かされている存在で、死は大いなるいのちの源へ還る旅路そんな死生観を、患者さんから感じる時があります。移ろう四季のなかで生かされ、自然や祖先を崇拝してきた日本人の遺伝子には、そうした信仰心が刻まれているのかもしれませんね。
以前、ある患者さんが私に話してくれたことがありました。「愛する妻や家族がいて、元気に働ける。なんでもないと思っていた日常のなかにこそ、最大の幸せがあったんだね」と。今日も太陽の光を浴びられる。道端の花を綺麗だなと感じられる。そういう一日一日を構成するすべてに、自分が生かされでいるのだと思えるようになったそうです。
そんな患者さんとふれあう度に、人生は今、この勝間が素晴らしく、感謝して生きていくことが大切なんだということをあらためて教えられます。
最後のプレゼント
在宅ホスピスに至る経緯について教えてください。
私が大学病院に勤務していた当時は、「患者さんの死は医療者の敗北」という空気が蔓延していました。もちろん患者さんの治癒はだれもが望んでいることです。しかし一方で、延命措置を施され孤独のうちに亡くなられていく患者さんを、数多く目の当たりにしてきました。
そんな時、二十三歳の女性の患者さんと出会いました。彼女は膵臓がんが肺に転移し、病状はかなり深刻なものでした。
<回復の望みのない彼女が、このまま病院で最期の時を迎えていいのだろうか>。悩んだ末に、「何か望みはある?」と聞いてみたんです。すると彼女は「家に帰りたい」と。その後、ご家族の同意と退院許可を得ることができ、私は病院に内緒で、彼女の家を往診するようになりました。彼女は何より、家族と一緒に過ごせることを喜んでいました。そして三か月後、お母さんの胸の中で、安らかに息を引き取ることができたのです。
この体験のあと、しばらくして私は、イギリス人の夫の仕事の関係で、イギリスに移り住みました。運命的と言うのでしょうか、この国こそ、ホスピスの発祥の地だったのです。
当時のイギリスは、市民運動によって、病院とは独立した形でホスピスの施設が立ち上がっていました。末期がんの人がホスピスに通い、必要なら入院もでき、また家で死を選ぶこともできる。患者さんは自分が助からないことを知っているのに、だれもが近づいてくる死に飲み込まれていないんですね。皆が明るく、今この時を、しつかりと生きていたのです。
私はこうした患者さんとふれあううちに、日本の病院で苦痛に耐えている患者さんのことが、再び気になりだしました。そして十二年前、夫と相談して、故郷の山梨県で在宅ホスピスを兼ねた「ふじ内科クリニック」を立ち上げたのです。
これまで、患者さんとのふれあいの中で、特に印象に残っていることはありますか?
患者さんと出会う度に、次々と思い出が紡がれていくという感じです。敬老の日に、お孫さんやひ孫に見守られて他界された九十一歳のおばあちゃん。亡くなる直前まで、笑顔でお孫さんの幼稚園の送り迎えをされていた女性……。先日亡くなられた男性とは、最期の時をどのように迎えるか、とことん話し合いました。別れの悲しみは消えませんが、患者さんは身をもって「いのちは希望」だと私に教えてくれました。
昨年、お母さんを看取られたご家族がいました。皆共働きでしたが、最後の一か月間、家族全員が介護休暇を取り、誠心誠意お母さんの介護をして最期を看取られたんです。離れて暮らしていた兄弟が、もう一度子どものころの家族に戻り、手を取り合って一つ屋根の下に集う。それで兄弟の粋が、より固く結ばれたそうです。そういうケースは少なくありません。きっとそれが、亡くなられていく方からの、最後のプレゼントなんですね。
ですから在宅ホスピスは、患者さんが死を安らかに迎えることだけが目的ではないんです。最期の瞬問までいのちを生ききった患者さんから、家族が生きる希望をもらい、また同時に、その姿からいのちの尊さを学ぶ場なのだと思います。

いのちの温もりを味わう
全国で講演活動をされているそうですが、今、l番伝えたいことやお感じになっていることはなんでしょう。
在宅ホスピスと言うと、自分たち家族には無理だと思われる方も多いかと思いますが、医療者のアドバイスを受け、介護休暇や介護保険などをうまく利用できれば、可能なご家族は少なくないと思います。愛する人の看護を自分たちの手でしてあげられたことが、きっと、あとあとその家族にとって大切な思い出になると思うのです。
以前、講演会場で永六姉さんと対談させていただいたことがあったのですが、永さんはお母様が息を引き取られる時に、ずっと抱かれていたそうです。すると、最期の瞬間まで生きようとしているいのちの鼓動が、いのちの重みが伝わってきたと言います。
こうしたいのちのふれあいは、最期の看取りの時だけでなく、いのちの誕生の時にもすごく重要だと感じています。子どもの物心がつく間、しつかりとお母さんがお子さんと向き合い、いのちの温もりを与えてあげる。そうして育てられた子どもは、必ず他者とも温かい関係を作れるのではないでしょうか。
自分が誕生した時に味わったいのちの温もりを、親の最期の時に、再び親子で向き合って交換し合う。だれもが、そうしたふれあいを自然に持てるような社会になれば、これほど豊かで幸せな国はないと思います。今、そんな願いを持って、私はこの仕事に取り組んでいるのです。
(Yakushin 2007年5月号より抜粋)
