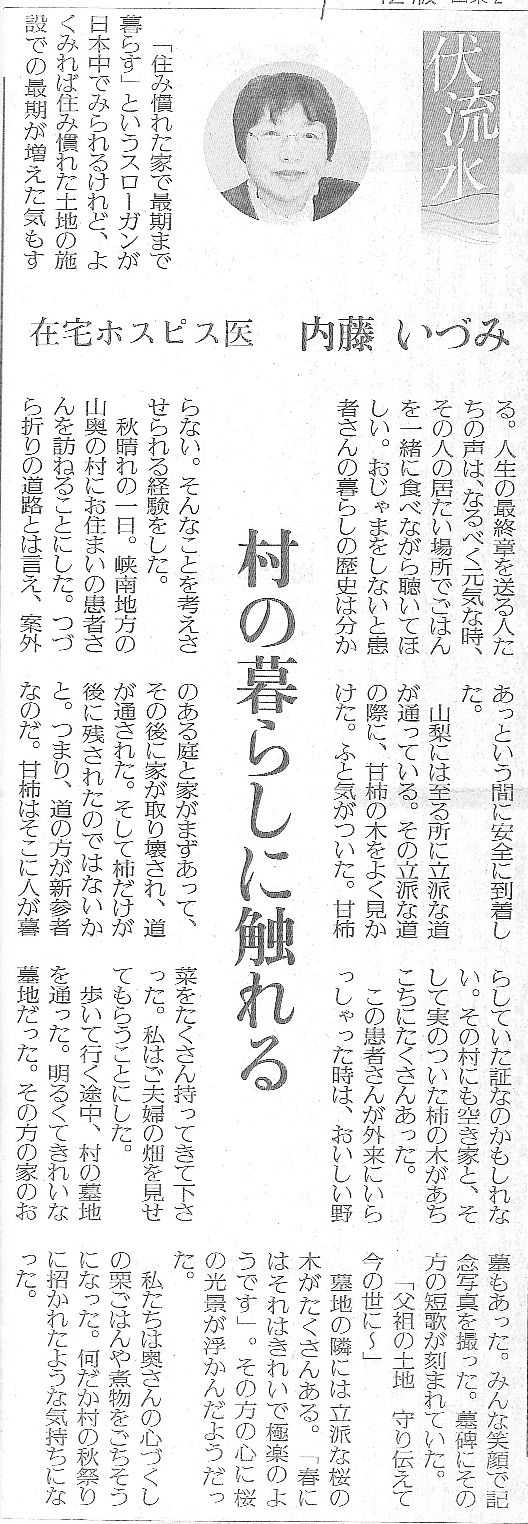悲しみ不安と向き合う
 2011年11月6日山梨日日新聞より
2011年11月6日山梨日日新聞より
大切な人を失ったとき、人は悲しみをどう乗り越えればいいのか―。日本ホスピス在宅ケア研究会山梨支部の「いのちを学ぶ講演会」で、終末期の患者や家族と接してきたバースセラピストの志村季世恵さん(東京)と在宅ホスピス医の内藤いづみさん(甲府)が講演と対談を行い、悲しみに向き合うこと、誰かと分かち合うことをポイントに挙げた。
内藤さんは徹底的に落ち込むことの必要性を指摘。「落ち込むことが怖くて、だましだまし、中途半端なところにぶらぶらしている」。大切な人の喪失に直面したとき、「底」まで落ちることができない人が多いのが現実だという。
「自殺する≒死にたい」と絶望を口にした患者でも、とことん落ち込んだ後に立ち直る姿を目にしてきた。「絶望を味わい尽くしたとき、心は浮かんできて、自分を取り戻すことができる」
志村さんは、自身も悲しみに対して向き合うことを実践している。「『底』であらがわずに静かにしていると、誰かの言葉がふと浮かんできて救われたりする」
一方、福島県の子どもの支援活動を通じて関わっている、母親たちの放射能への不安にも触れ、「どうにもならない不安は忘れてしまうのではなく、苦しい現実を受け止め、向き合わないと乗り越えられないのでは」と投げ掛けた。
では苦しい現実と向き合うにはどうすればいいのか。内藤さんは「語る相手をつくることがとても大切」と言う。
3割が楽しく、1割が悲しく、6割はどちらでもいい内容―。
内藤さんは人の記憶に関する研究結果を紹介し、「悲しい記憶をゼロにというのは自然ではない。悲しい気持ちを浮き上がらせて誰かに伝え、消化していくと、いつか1割になる」。
病気の夫を自宅でみとったという来場者の女性も体験を語った。「つらい気持ちを詩にして投稿した。誰かが読んでくれたと思うと、だんだん元気になれた」
志村さんは、みとった人たちから「バトン」を渡されたという。死を前にして気付いた、人とのつながりや人を信用することの大切さ。それを今生きている人に伝える役目を託された、と語る。
内藤さんは、苦しい治療のためにいそうした最期の意思表示をする大切な時間が失われてしまっている人も多い、と指摘した。「誰かの役に立ち、亡くなるときに誰かにメッセージを残せる、そんな人生が送れたら幸せ。そのための手伝いは、家族や友人にもできる」と話した。