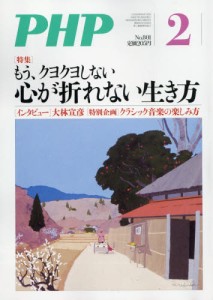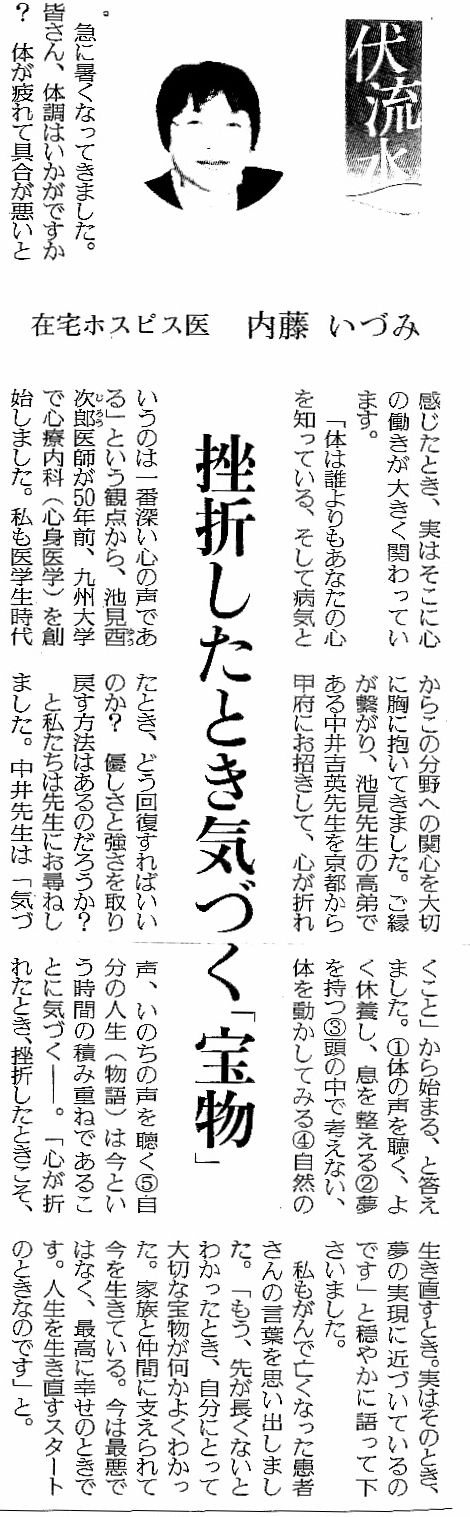最期のときを家族と 声なき声を聴き遂げる
相川節子さん(89)=仮名=は、、外来に来るたびに「先生、あと、どのくらい生きられますか?」と聞く。血圧はは安定。甲州弁で「飛びっこ」(短距離走)」の得意だった人らしく、健脚で心臓は丈夫だ。「まだまだ先は長そうですよと答える。
91歳の石田章子さん=同=はひとり寄らし。最近「10分前のことも忘れやすいが、買い物の道順は迷わない。自立し、今の生活継続を希望している。「人には、ちょうど良い寿命ってのがありますからねぇ。私はあとどのくらいでしょうか」と聞いてくる。内科的には問題なく、「まだまだ大丈夫ですよ」と答えると、「あら困ったこんだ…」と言いつつ、うれしそうだ。希望を失っていない。
「生きる」ことは「生きたい」という希望の力で紡がれている気がする。
お二人のように、話せる方は協力しやすい。安藤絹代さん(78)=仮名=は度重なる脳梗塞で入院が長引いた。後遺症で話せなくなり、飲み込みも難しい。入院先で流動栄養を直接、胃に入れる「胃ろう」を提案され、娘さんは承諾した。「お母さん、本当にこれでいい?」と何度も聞いたという。もちろん、返事はない。元気なときに話し合ったこともなく、娘さんが決定した。
帰宅後、私が主治医になった。娘さんは毎日、流動食をゆっくりチューブに入れた。しかし、安藤さんはもどし始めた。量を減らしても、薄くしても。
肺炎で発熱する日もあった。
私は長年の経験で、安藤さんが「命を燃やすエネルギーはもういらない」と、表現しているように思えた。娘さんも同様に感じていた。点滴への切り替えを提案すると、娘さんは身内にも了解を得て、「母は入院中、忍耐強く過ごしました。もう、望まない治療はさせたくない。お母さん、このチューブはしばらくやめる?」
チューブを外すと、安藤さんはほほ笑んだようだった。やがて吐き気もなくなり、落ち着いた。脱水予防の点滴はあるが、見舞いにも穏やかだったという。「家で看られて幸せ」。娘さんはそう話した。
2日後、お母さんは笑顔でこときれたという。駆け付けると、娘さんは言った。「母は与えられた寿命を生き切りました。最期に母の願いを聞き届けられた気がします」
声なき声を聴くのは難しい。しかし最期の日々を囲む人が、本人と心から交流を持ち、穏やかな気持ちでいることが聴き遂げる要素ではないかと思う。
2009年1月14日 産経新聞より抜粋