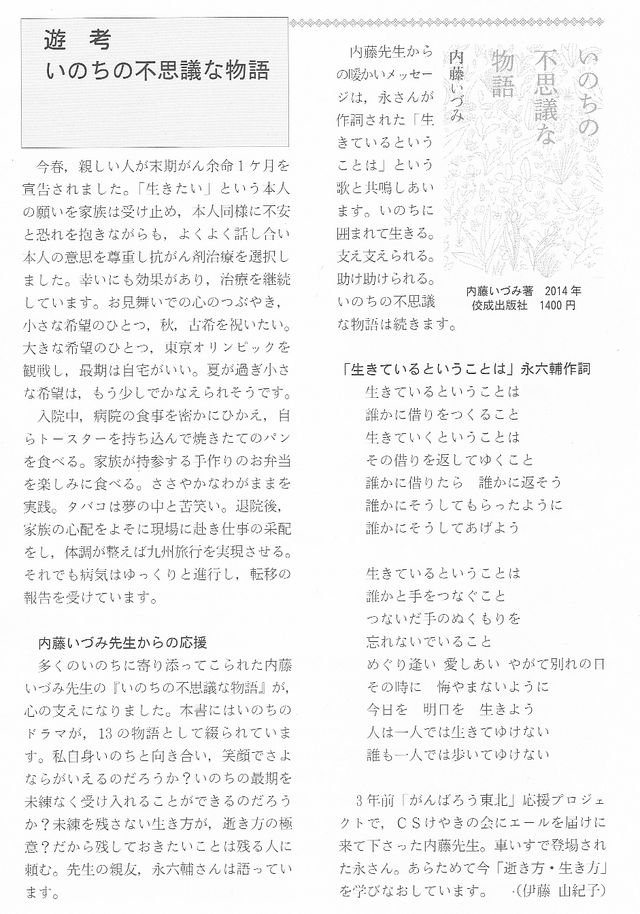気になる女性 内藤いづみさん
ふぁいんピープル「いい人 いい話」
1985年10月・11月号からの抜粋、文・遠藤周作様。
医者としての苦しみを本気で苦しみ、それを乗りこえようとしていた・・・
ずっと年下の世代でも心から尊敬できる女性がいる。
その人は若い女医で、内藤いづみさんという。

彼女と知りあったのは三、四年前、私が「心あたたかな病院がほしい」という文章を新聞に書いた時だった。日本の病院はたしかに技術的には一流の水準になってはいるが、しかし、患者にとって「あたたかい」とは必ずしも言えない。経験のある人も多いだろうが、無用な苦痛、無用な屈辱を与えすぎるからだ。だから私は「心あたたかな病院がほしい」と言う文章をつい書いたのである。
反響はすごかった。毎日、十通二十通と手紙がきた。そのなかには心ある医師や看護婦さんの手紙もまじっていた。この人たちは自分たちの組織のなかの苦境をのべ、あわせて医療には無学の私に医療の実態をもう少し勉強してほしいと、忠告してくれたのである。
これらの手紙のなかに―今でも憶えているが―ブルーの封筒で女子学生らしい可愛いい文字で、内藤いづみというこれも可愛いい名前の一通があった。はじめは女子大生の便りかと思って読んでいると女医と書いてある。しかも私のこのキャンペーンに讃意を示し、協力したいのですという言葉があった。
これが切掛けで内藤いづみさん―いや内藤先生と知りあいになった。会ってみると若い、美しい、そして心の本当にやさしいお嬢さんだった。
ある大きな病院で彼女は勤務していた。末期癌の患者を何人も担当し、現代の医学では絶望的なことを承知しながら、彼等の昔しみと向きあう毎日を送っていた。私は彼女からその時の心の苦しみをきかされ、たとえ女医とはいえ、二十代の若い娘がそのような苛酷な現実にさらされることは良いのか、悪いのかがわからなくなってきた。
尊敬する聖路加病院の日野原先生にこのことを相談すると
「一人前の医者は皆、そのような状況をへてきたのです」と先生はおっしゃった。
しかし私には釈然としなかった。毎日人間の苦しみと死とにふれれば、誰だってやがて他人の死や苦しみに無神経になり鈍感にならざるをえない。私は若い内藤先生にそのようになってほしくはなかったのだ。
だがそれは私の文字通り取りこし苦労だった。内藤いづみさんはそんな、心のすり切れた医者ではなかったのである。彼女は心底からあたたかな思いやりのある先生だったから、その後も自分の医者としての苦しみを本気で苦しみ、それを乗りこえようとしていた。
「患者さんが治るのなら何でもやってみます」 私は、これが本当の医者だと思った
一年半ほど前内藤いづみ先生は一人の女子学生の主治医になった。この女子学生は可哀想に手おくれになった癌の患者だった。
いづみ先生は自らの妹のようなこの女子学生を救うためにありとあらゆる治療を試みた。上司の先生たちのきめられた化学療法がもう効果がなくなると、普通の医者なら馬鹿にするあの丸山ワクチンもうった。
その頃、私は、主婦の友社の「私の健康」という雑誌で、正統医学がかえりみない色々な治療法の対談を行っていたから、大阪で加藤という人が癌患者にミルク療法というのを行い、かなりの効果をあげていることを知っていた。
私はいづみ先生のような西洋医学者にその話をしても軽蔑されるかもしれぬと思いながら、患者を助けようと必死な彼女の姿にうたれて、この治療法の話をした。「私の健康」のH編集長にも紹介した。
「やってみます。あの患者さんが治るのなら何でもやってみます」
といづみ先生は答え、病院から家庭に戻された病人につきそって大阪まで行った。その時彼女は若い女医の身でありながら重い酸素ボンベを背に背負って飛行機に乗ったのである。
私はその話をきいた時、これが本当の医者だと思った。
一人の患者を助けるため、これだけの努力をしてくれる医者はそうざらにはいない。
「いづみ先生、その気持を忘れないでください」
と私はすべての患者の思いをこめて、電話でそう彼女にたのんだ。
だが既に体のすべてを侵していた病魔は、いづみ先生の努力にかかわらず、その女子学生の命を遂に奪ってしまった。いづみ先生はしばらくそのショックで辛そうだったが、そこから多くのものを、医者として人間として学んだにちがいない。私はそんな彼女の医者としての成長をじっと見守りたかった。
いづみ先生にいつか診療所を作ってあげたい、というのが私のひそかな願いである。この女医なら安心して信頼できるからだ。
どなたか、彼女のため、私と協力してくださる人はいないだろうか。彼女に会ってくれれば、きっと私とおなじ気持になると思うのだが。