レイチェル・カーソンについてお話を
私の古い友人で編集者である川村まさみ様との往復書簡、第一回目の往路です。
いづみ先生
東京はこの冬初めての大雪です。雪が降ると、やっぱりワクワクします。身辺を温かくして、飲み物食べ物を手の届くところに置いて、読んだり書いたりすることに時間を忘れる。昼間からこれが楽しめるのは、こうして雪に降り込められていてこそです。
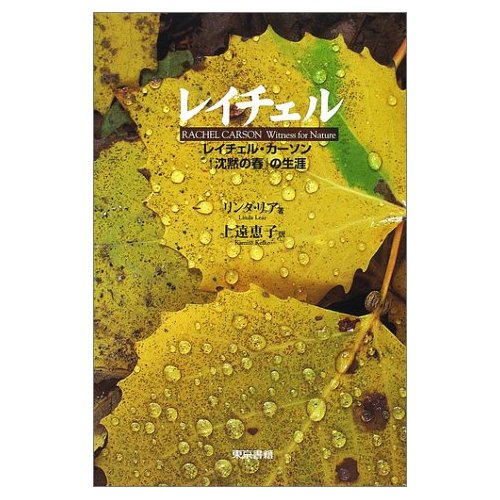 いづみ先生から、レイチェル・カーソン 注)についてお話しませんかとお誘いを受けて、六年前に編集に携わった大部の本、『レイチェル レイチェル・カーソン「沈黙の春」の生涯』を少し読み返していました。思えば、この本を仕上げたあと仕事の変わった私がそのことをお知らせしたら、イギリスに向かう機中で読みたいとおっしゃってくださって、出来たてのような本をお送りしたのでしたね。
いづみ先生から、レイチェル・カーソン 注)についてお話しませんかとお誘いを受けて、六年前に編集に携わった大部の本、『レイチェル レイチェル・カーソン「沈黙の春」の生涯』を少し読み返していました。思えば、この本を仕上げたあと仕事の変わった私がそのことをお知らせしたら、イギリスに向かう機中で読みたいとおっしゃってくださって、出来たてのような本をお送りしたのでしたね。
二百人以上への取材をもとに書かれた八百ページ近いこの翻訳書は、でもレイチェルの息遣いさえ感じられるほどの筆遣いで、胸の震えるような感動を覚える本でした。その感動を、すっかりここでお伝えすることは無理ですが、彼女の伝記の決定版に編集者としてとことん付き合った経験から、お話できることがあるかもしれません。
先生、覚えていらっしゃいますか。レイチェルは晩年、みずから「病気のカタログ」と嘆くほど、いろんな病気に苦しみました。やはり一番つらかったのはがんでした。原書にも、はっきりbreast cancerとは書かれていませんでしたが、原発はおそらく乳がんでした。そのことだけで、レイチェルが同じ女性としてとても身近に感じられると言ったら、レイチェルはなんと言うでしょうか。写真からも分かるようにレイチェルは楚々として美しく、大人になってからはお洒落にも気を配る女性らしい女性だったのですから、なにも乳がんまで持ち出さなくても十分同じ女性よ!って気を悪くされるでしょうか。
でもやっぱり、レイチェル・カーソンは偉大なのです。一九六二年に『沈黙の春』で農薬、ことに殺虫剤の害を告発し、環境問題にいち早く警鐘を鳴らしたその勇気は、私たちを奮い立たせてくれます。だからこそ女性に崇拝者が多いのですが、そうして崇拝してしまうと、普通の人間としての弱さに触れることが怖くなるようで、この本も賢く強く美しいレイチェルばかりでなく、十分に弱い一人の人間を見事に描いているせいか、読む人によっては拒否反応もあると聞きます。私も、もっと若いときに読むことになっていたら、受け入れがたいものを感じたかもしれません。とはいえそれは、決してセンセーショナルなものではなく、ごく普通の人間として、「書く」という作業の重圧や、家族の世話や、金銭的な心配や、人間関係に悩む、あたりまえの姿なのです。やがて、生身の人間として女性として乳がんにも罹るのです。
しかし、その果てに、病と闘いながらも『沈黙の春』を著し、それに続く称賛と非難、両方の嵐に耐え、産業界からの攻撃に立ち向かい、ケネディ大統領時代の上院で証言をやりとげる、強い強いレイチェルがいます。でも、公の場では冷静に振舞いながらも、その場を離れれば放射線治療の副作用で強烈な吐き気に苦しむレイチェルがいました。やがては講演会の演壇でも車椅子を余儀なくされるレイチェルでした。
幼いときから「作家になる」と固く心に決める意志と才能をもちあわせたレイチェルでしたが、一足飛びにこれほど強靭な精神力を得たわけではないと思います。自分の才能を開花させながら家族を支えることに追われ、独身を通した彼女は、家族からの愛情や友情を人一倍必要とした女性でした。では、何が彼女を強くしたのでしょうか。最後まで友人からの愛情が支えではありましたが、自分のなかから湧いてくるものとしては、やはり自然の美しさをかけがえのないものと思う気持ちだったと思います。病を得て自分のいのちの先をみつめるようになって、それは驚くべき強さをレイチェルに与えたのです。とはいえ、体調の悪いときの、なんと切なく心細かったことでしょう。
みなさん感じていらっしゃるはずですが、環境問題って、“地球を救おう!”なんていう傲慢な言葉で語られるものではなくて、自分のいのちを謙虚に振り返ったときに、おのずと身の処し方を考えるようになる、それが出発点だと思うのです。だから、いのちのことも、環境のことも、声高にではなくて、その切なく心細い声で語ってこそ、本当に人に伝わるのかもしれません。『沈黙の春』は、病のなかで書かれたからこそ、人に伝わり、人を動かす力を持ったのかもしれないと、いま思います。
いづみ先生、先生は日々こうした切ない場面に立ち会っていらっしゃいます。
先生のレイチェルへの思いを、お聞かせください。
リファレンス
レイチェル レイチェル・カーソン 「沈黙の春」の生涯(東京書籍)
生物学者としての目と、作家としての豊かな感性が、環境問題を世の中に問うた不朽の名作、「沈黙の春」を生んだ。
川村まさみ様との往復書簡、第一回目の復路です。
レーチェル・カーソンという女性 往復書簡 その1(返事)
川村さんへ
おたより嬉しかったです。ありがとう。
先日の雪に閉じ込められて、お部屋で書簡をしたためている姿を想像したら、あなたの静かな明るいエネルギーが私まで伝わってきました。
私は今朝4時半に起きて、大学受験に向かう子供を送り出しました。そう!もう2人目の子が18歳です。甲府盆地の道端には残雪が残り、頬に当たる風の冷たいこと。今は朝焼けを見ながら、ミルクティーを飲んでいます。その静けさ。自分だけの自由な時間。こんなにのんびりしたのは、何だか久し振りな気がします。心の中の妖精が目を覚ましたような感じです。自然の中の自分という存在を感じるためにも、静寂さが必要ですね。大人の日常はDoing(何かをすること)で忙しすぎます。Being(そこにいる)ということを、もっと思い出したいです。

「センス オブ ワンダー」でレーチェルはこう言っています。
『子供たちの世界は、いつも生き生きとして新鮮で美しく、驚きと感激にみちあふれています。残念なことに、私たちの多くは大人になる前に澄み切った洞察力や、美しいもの、畏敬すべきものへの直感力をにぶらせ、あるときはまったく失ってしまいます。
もしも私が、すべての子供の成長を見守る善良な妖精に話しかける力を持っているとしたら、世界中の子供に、生涯消えることのない「センス・オブ・ワンダー=神秘さや不思議さに目を見はる感性」を授けてほしいと頼むでしょう。
この感性は、やがて大人になるとやってくる倦怠と幻滅、私たちが自然という力の源泉から遠ざかること、つまらない人工的なものに夢中になることなどに対する、変わらぬ解毒剤になるのです。』
21世紀の大人たちは、子供たちの感性をしっかりと守る人になっているかは、甚だ心もとないです。自然に触れず、遠くに居る友人とさえ、テレビゲームで戦えるこの頃の子供たちのことがとても心配になります。
しばらくお会いしていないのに、レーチェル・カーソンを語る、という私の大胆で強引なお願いを引き受けて下さってありがとう。
川村さんとは10年以上前に、共通の友人の縁で知り合いましたね。優秀ですてきなセンスをお持ちの川村さんを、その友人は絶賛しており(本当にそうです!)、何とか3人で「ホスピス」関係の本を作りたいと、その頃何度も新宿辺りで作戦会議を開いたことを覚えていますか?楽しかったですね。10年前には「ホスピス」はまだあまりに重いテーマで、結局その時は本を誕生させることができませんでした。「死」についての本なんて、誰が買うの?という空気が濃厚でした。今、この分野は食傷ぎみと思えるほど、たくさんの本が出版されています。ほんの10年で、こんなに世の中は変わるのですね。
80年代に私は英国でのホスピス運動をみてきた感動を胸に、30代の大きなエネルギーを山梨県でのホスピス運動に捧げてきました。
「ホスピス?ホステスさん?」
という一般の方の感想から始まり、
「先生はクリスチャンですか?だからこういうことをするのですか?」
という問いが続き、私が
「クリスチャンの友人は多いですが、私の家は神道なんです。」
と答えると、怪訝な顔をいつもされました。医師たちからは
「病気を治さないなんて、ホスピスケアは医学ではない。患者を絶望させるだけだ。まあ、たまには私の末期がん患者さんのために、あなたを呼んでもいいよ。手を握って、カウンセリングしてあげてよ。それがホスピスケアでしょ?」
楽な仕事だと思われていることに対して
「いや、違う。まず身体の痛みを緩和することに集中し、そして心、社会、魂と続くトータルぺインへの関わりなんです。」
と、力説してきました。諏訪中央病院の院長だった鎌田実先生は、真っ直ぐに私の言うことを受け止めて応援してくれた、数少ない医師のひとりです。振り返ってみると、「いのちは希望」というメッセージを私はずっと握りしめていました。多くの患者さんと出会い、20年経った今では、改めて確かにそうだと思えるのです。
こんなことを長々と書いたのも、私のようなささやかな人間でも、権威や組織に所属せず、その時代には少し新しいことを社会に発信しようとすると、「生意気だ。」などとバッシングに近い圧力を何度も体験したからです。しかし、生病老死、いのち、生と死、それは、人権、宗教、性別、年齢を越えて私たちにとって、とても大切なことだと信じて揺るがなかったのです。頑固に私は行動を続けました。
日本の社会も変わり、今は真剣に生と死の医学を受け止めて考えて下さる人が増えました。だから、私のささやかな反骨の体験から想像してみても、「沈黙の春」という本で、真実ではあるけれど、利益に関連する多くの企業や団体にとって耳痛い内容の本を出版し、発言し続けたレーチェルの勇気と体力と知性に脱帽するしかないのです。今こそ世界中、環境問題は地球の未来を握る大問題となっていますけれど、当時の人たちにとっては驚きの発言だったことでしょう。環境破壊により、鳥の鳴かない春が来るかもしれないなんて、全く想像もできなかったはずです。
レーチェルは派手な人ではありません。しかし、凛とした美しい女性ですね。伝記を読むと、一生独身で、家計を支えながら自分の病と戦い、必死で働き、あの本を書き上げた様子がよく分かります。あなたの言うように、何が彼女の信念をそこまで支えたのか・・・・私もふと不思議に思える時があります。
 実は私には尊敬する5人の女性がいます。マザー・テレサ、エリザベス・キュブラー・ロス、シシリー・ソンダース、パールバック、そしてレーチェル・カーソン。それぞれの伝記を読むとよく分かるのですが、どの女性も自分の人生の抱えきれないほどの悲しみを背負いながら、でも真っすぐに、一生頑固に、信念を曲げず発信し、行動してきました。どんな権威にも、脅しにも屈しない、媚びない生き方に通じるもの。
実は私には尊敬する5人の女性がいます。マザー・テレサ、エリザベス・キュブラー・ロス、シシリー・ソンダース、パールバック、そしてレーチェル・カーソン。それぞれの伝記を読むとよく分かるのですが、どの女性も自分の人生の抱えきれないほどの悲しみを背負いながら、でも真っすぐに、一生頑固に、信念を曲げず発信し、行動してきました。どんな権威にも、脅しにも屈しない、媚びない生き方に通じるもの。
個人的な欲から離れた、近づきがたいほど凛々しい姿。5人の類まれな知性を持つ女性が行き着いたところ、それは彼女たちが行き着いたいのちのエネルギーが教えてくれたこと、いのちは繋がっている、いのちは欲張らない、いのちは未来への希望。そして揺るぎない“愛”の力の大きさではないでしょうか?
私の在宅ホスピスケアの仕事は、死にゆく方々との苦悩に向かい合い、無事、向こう岸へ送り届ける、渡し舟のような役目です。私の仕事柄か、勘違いして、私のことを神性?な存在だと思い込み、一方的に尊敬して下さる方々も時々います。
とんでもない!
育ち盛りの3人の子供の子育てに日々悩み、従業員には少しでも多くの給料をあげたい、と経営手腕の乏しさに眉間のしわを深くし、50歳を過ぎたら急に進行するメタボの体にガックリする、本当に拙い、小さな存在にすぎないのです。
しかし、その小さな存在の私が、終わりゆくいのちの神秘に触れ、いのちの希望を得て、頑固にひたすら“怖くないよ、大丈夫です”と死にゆく方々のトータルペインに何とか寄り添っているのです。
あの「レーチェル」にまつわるお話を、次回はもう少し教えて下さいますか?私はモナーク蝶の大群を見ているシーンが、心に深く刻まれています。
本文中の写真で紹介している本(上から順に)
・センス・オブ・ワンダー (新潮社) レイチェル・L. カーソン (著)
・人生は廻る輪のように (角川書店) エリザベス キューブラー・ロス (著)
・シシリー・ソンダース?ホスピス運動の創始者 (日本看護協会出版会)シャーリー・ドゥブレイ (著)