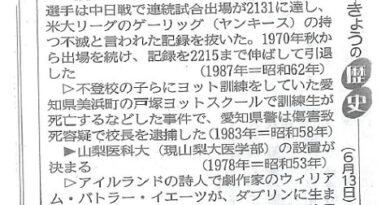いのちのバトンを渡す
「あけぼの」2012年11月号、「特集・生と死のはざまで―次世代につなぐいのち」より抜粋
私は自分でもいささか楽観的な性格であると思っている。そうでなければ、この三十年間ひとすじにいのちの最期に関わるホスピスケアの啓発と実践活動を続けて来られなかっただろう。
思い出してみると、医学部に入ってからはいのちに向かいあう度に疑問が大きくなった。
「なぜ、がんの告知が本人へされず、まわりが選択するのか?」
「なぜ、がん患者は体の痛みを充分に和らげてもらえないのか?」
「なぜ、末期がん患者は家に帰れないのか?」
そんな未熟な私の悩みを聞いて下さったのが作家の遠藤周作さんだった。そのご縁もあって、あけぽの誌上で対談もさせて頂いた。
私の医者になってからの三十年はホスピスを学ぶ旅たった。遠藤先生が御存命だったら私にこう言うだろう。
「あんなに繊細そうだった若き女医が今や貫禄充分ですなあ。どうだね、あのときの君の疑問は少しでも解けたのかね? 医者と神父は人の魂に手を突っ込む仕事だとぼくは
言ったけれど、君はそんな医者に近づけたかい?」
私はもし先生に会えたなら、こう答えてしまいそうだ。
「先生、心に寄り添う優しい告知にはなっていませんが、がんの告知はほぽ百パーセントになり、真実を知り、本人が未来を選びやすくなりました。モルヒネなどのがんの疼痛
によく効く薬を昔より多くの医者が使うようになりました。ホスピスと言いませんが、緩和ケア病棟は全国に増え、末期がん患者さんが入院できます。しかし、がんの痛みから解
放され、笑顔の患者さんがもっと増えていいはずなのに、私が想像するほど増えてはいない気がします」
「それはなぜなのかね?」
「体の痛みから解放されて、初めて自分の心や魂に向かい合ったとき、自分がこの世から消えてしまう恐怖にさいなまれるからだと思います。そのとき支えてくれるものが乏しいのです。
魂に手を突っ込めているかはよく分かりません。でも、言葉にならない会話を危篤の患者さんとすることもあります。患者さんの肉体は病によって衰えているけれど、いのちの
エネルギーは最後の一息までメラメラと燃えている。そのいのちを尊重します。死を怖がらなくても大丈夫です、と」
「そのいのちは天国に行くんだろうか?」
「皆さん亡くなった後、とても良い笑顔になりますから、多分良い所に行っています(笑)」
私はもうヨチヨチ歩きの新米医者ではなく、充分看取りの経験を積んだ医者だ。若き私の持った疑問のいくつかはこうして現代医療の中で改善したけれど、日本の社会で人間の
心と魂の逞しさは成長したとは思えない。自己中心主義に傾いている。
そして、病気以外でもきちんと真実を告げてもらい、未来の子どもたちのために選択していくことが、2011年3月11日の大震災の原発事故以来、重要になっている。私たち
は自立できる人間として、原発事故の事実をきちんと伝えられてこなかったと思う。事実を知らなければ、根拠なき楽観主義に頼ったり、いわゆる風評被害に踊らされ、不安にさ
いなまれる。
トリアージ(災害時、病気やケガの緊急度・重要度を判断して、治療の優先順位を決めること)は厳しい。
しかし、今の日本社会はトリアージが必要だとだれかが批判を覚悟で言うときが来てはいないだろうか?
今の現実は、正社員の減少。税収の減少。子育てへの不安。少子化の拍車。昨年度で八兆円を超す介護保険総費用の増加。弱い者、老いた者を大切にするシステムはとても大切だ。
熟成した社会だからこそできることだ。しかし、未来の子どもたちに希望を持ってこの社会のいのちのバトンをきちんと渡すためには、前例主義から脱して、これ以上欲張らず自然の中に共存する質素な幸せに感謝して大人が肝を据えて生ききる姿勢を見せることしかない。